当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
本記事では、住友林業で注文住宅を建てたkikorist夫婦が、住宅ローンに必要な基礎知識について解説します。
住宅ローンを組む際は様々な選択肢があります。「固定金利 or 変動金利」、「元利均等払い or 元金均等払い」、「団体信用生命保険(団信)」、「繰り上げ返済する or しない」などなど。
例えば、5,000万円を35年の返済期間で借り入れする場合、低金利の変動金利(0.5%)では返済総額5,450万円ですが、固定金利(1.5%)では6,430万円と、返済額に約1,000万円もの差が出ます。
では、住宅ローンを利用する全ての方にとって低金利の変動が正解というと、必ずしもそうではありません。
個人の状況や考え方によって何が正解かは変わります。たとえ総支払額が増えても将来見通しの確実性を重視する人もいれば、リスクを取って低金利のメリットを重視する人もいます。

重要なのは、なぜその選択をするのかということ。

「何となく」「周りがそうだから」「ハウスメーカーや銀行の担当者がオススメするから」ではなく、ライフプランや夫婦の考え方を明確にして決めるようにしましょう。
本記事では、個人的に住宅ローンで知っておいたほうがいいと思われる知識を総まとめにしています。

なかなか1つの記事で必要な情報がまとまっているというサイトがなかったので、本記事を参考にしていただけますと幸いです。

住宅ローンについて知っておいたほうがいいことを全て書いたら長文になってしまいました…汗
長文ですが、いずれも重要な内容で、本記事さえ読めば住宅ローンで必要な知識が全て身に付きます。ご一読ください。
金融機関(銀行)の選択
メガバンクと呼ばれる大手銀行や地方銀行、信用金庫、労働金庫、農協など、さまざまな金融機関が住宅ローンを提供しています。
最近では低金利を前面に打ち出したネット銀行が提供する住宅ローンが人気です。大手銀行では金利0.4%~0.5%台が一般的なところ、ネット銀行では0.3%台も珍しくありません。

auじぶん銀行の金利(2023年4月時点)

ネット銀行は店舗を持たずネットだけでほぼ手続きが完了するため、店舗維持費や人件費がかからず、審査にもAIを導入するなどコスト削減を進めているため、低金利の住宅ローンが提供できるのです。
では、ネット銀行が誰にとってもベストかというとそういうわけではなく、ネット銀行は、与信審査が厳しいという特徴があります。事前審査ではAIなどを使って審査を1日前後で行うため、年齢や年収などによってはあっさり落ちるということがありえます。

実際kikorist夫婦も借換にあたって候補の1つであったPayPay銀行の事前審査に落ちています。

審査落ちの理由は開示されませんが、年齢(借入時に夫婦ともに30代後半)やクレジットカードのキャッシング枠(キャッシング枠はショッピング枠と異なり、借りていなくても限度額がそのまま借金と同じ扱いになるらしい)あたりが原因かなと…。

ちなみに、kikorist夫の会社の後輩夫婦(ペアローンで新規借入)もPayPay銀行は審査落ちとなり、auじぶん銀行は上乗せ金利になりました。
おそらく奥さんが育休中だからかな…。
審査によっては、申請した借入額満額ではなく、借入額を減らす(=不足分は現金で支払う)ことが貸し出しの条件になることもあります。
また、ネット銀行の多くは土地購入に利用できる土地先行プランや分割融資・つなぎ融資に対応していません。

住信SBIネット銀行や楽天銀行は土地先行対応、auじぶん銀行やPayPay銀行は対応していません(2023年4月現在)。

今は対応していない銀行においても、今後土地先行に対応した住宅ローンが登場する可能性はあります。
一方、メガバンクや地方銀行、信金などは担保価値なども含めて丁寧に審査をしてくれる傾向にあります。
特に、ハウスメーカーの提携住宅ローンでは、ハウスメーカーが手続きのサポートをしてくれたり、金利が優遇されたり審査が通りやすいといったメリットがあります。

提携住宅ローンについてはこちらの記事に詳しくまとめています。
また、メガバンクや地方銀行は、土地先行でも柔軟に対応してくれることが多いのも特徴。
住宅ローンの審査は複数の金融機関に依頼が可能です。低金利だからとネット銀行だけに絞らず、複数の金融機関の住宅ローンに審査を申し込んでおくと安心です。

審査通ったところから最適なところを選べばいいわけね。
住宅ローンの比較には「モゲチェック 住宅ローン診断」というサービスが便利です。ご自身が借りられる総額や審査が通る確率、金利や団信などを比較することができます(しかも無料!)。
各住宅ローンの金利をランキング形式で比較できるのも非常に便利です。

私たちもモゲチェックを利用して、金利を比較しました。

モゲチェックは完全に無料ですし、使ったからといって貸出金利が上乗せされるわけではないので、その点も安心。

むしろモゲチェック限定の優遇金利があったり。
モゲチェックの塩澤さん(@takashishiozawa)は、X(旧Twitter)でも住宅ローンに関する情報を発信されていますので、フォローしてみるといいのではないかと思います。
【爆安&爆速】モゲチェック特別金利、本日から始まります!今回はなんと0.48%です😍 しかも事前審査は最短3分で回答が出ます。
この爆安&爆速商品はモゲチェックだけの取り扱い!申込みは「住宅ローン診断」からどうぞ♫ ぜひオトクなローンをゲットして下さい😊 pic.twitter.com/ci5wJlvoxU— モゲチェック塩澤|住宅ローンアナリスト|皆さんが気になる疑問にズバリ答えます💁 (@takashishiozawa) October 1, 2025
固定金利と変動金利
住宅ローンの金利タイプには、大きく分けて「固定金利」と「変動金利」の2種類があります(借りた当初数年間固定でその後変動になるタイプや固定と変動を組み合わせたミックスもあります)。
固定金利
固定金利は、金利が借入期間中一定で変わらないタイプの商品で、借り入れの際に決定された金利が契約期間中変更されることはありません。
金利の変動リスクがなく、融資実行時の金利で毎月の返済額と総支払額が確定するため、将来見通しが立てやすいのがメリットです。
一方、金融機関にとっては固定金利は長期間にわたって金利を固定するリスクがあるため、固定金利は変動金利よりも金利が高く設定されているのがデメリットと言えます。
変動金利
変動金利は、その名前の通り半年ごとに金利が変動するタイプの商品です。
変動金利は(同時期で比較すれば)固定金利と比較して金利が低い点がメリットです。特に最近(2023年4月時点)では、ネット銀行同士の変動金利の引き下げ競争が激しく、適用金利が0.3%を切る金融機関もあります。
一方、変動金利は金利上昇のリスクがあります。借りる時点では固定金利よりも低金利だったとしても、金利上昇が続ければ固定金利の金利を上回ることもありえます。
また、毎月の返済額が変動するため、将来的な予算の立てにくさもデメリットです。

10年、25年後に子供が大学に進学してお金がかかるときに、金利が上がったりすると計画が狂ったり…。
変動金利を選択する場合は、将来金利が上昇した場合でも毎月の返済が問題ないか、もしくは繰り上げ返済ができる手持ち資金を用意できるかを確認したほうがよいでしょう。

各銀行の住宅ローンのページでは金利を自由に設定して、月々の返済額をシミュレーションできるようになっています。
金利はどのように決まるのか
適用金利
住宅ローンで我々が借りる実際の金利は「適用金利」と呼ばれる金利です。一般に住宅ローンの「金利」と言えば、「適用金利」を指します。
各銀行には貸し出しの際の基準となる「店頭金利(基準金利)」があります。この「店頭金利」から個人の与信状況に応じて一定の金利を引き下げています。この金利の引き下げ幅を「優遇金利」と言います。

適用金利=店頭金利-優遇金利

「適用金利=店頭金利-優遇金利」ということね。
銀行の住宅ローンのウェブサイトなどで表記されている金利は、優遇金利が最大のとき、つまり適用金利が最低だった場合の金利です。各銀行の所定の与信条件をクリアした場合にのみ、この金利が適用されます。

表記されている金利は優遇金利が最大だった場合(出典:じぶん銀行)
したがって、収入や勤続年数が銀行の基準を満たさなかった場合は、最優遇金利から金利が上乗せされされることがあります。
店頭金利や優遇金利(金利引き下げ幅)は、金融機関によって異なります。
店頭金利(基準金利)
続いて、店頭金利がどう決まるのかを解説します。
そもそも固定金利と変動金利は、金利決定のメカニズムが異なります。
固定金利は、新発10年国債利回り、いわゆる長期金利に連動します。

新発10年国債の金利と大手銀行の固定金利(店頭)の推移(筆者作成)
変動金利は、(銀行によって異なりますが)基本的に短期プライムレート(短プラ)に連動します(短プラ+1%程度)。短プラは銀行が信用力の高い企業に融資をする際に適用される貸出期間1年以内の最優遇金利(=最も低い金利)のこと。
短期プライムレートは日銀の政策金利とほぼ連動しています(政策金利に銀行ごとに定める一定の金利を上乗せ)。

変動金利は短プラをもとに決定され、短プラは政策金利をもとに決定されるってことね。

大手銀行の短期プライムレートと変動金利(店頭)の推移(筆者作成)
変動と言いつつ、大手銀行の短期プライムレートは、2009年1月以降2023年4月まで1.475%から変動していません。

これは日銀が長期間ゼロ金利政策、マイナス金利政策(2016年以降)を続けているため。
政策金利がほぼ0で変動がないため短プラも変化がないのです。
そのため、短プラに連動する変動タイプの店頭金利も2009年以降は2.475%で一定となっています。
ただし、店頭金利は一定でも変動金利の適用金利は低下を続けています。

大手銀行の店頭金利と適用金利の推移(筆者作成)
これは店頭金利(基準金利)からの金利引き下げ幅である優遇金利が拡大しているため。
短期プライムレートに変動がないため店頭金利は変わりませんが、銀行間の競争が激化したため、各銀行は優遇金利を拡大することで適用金利を下げているのです。
そのため、現状では最も低い銀行では0.3%前後まで適用金利が低下しています。

auじぶん銀行の適用金利(2023年4月時点)
なお、一度適用された優遇金利は契約期間を通じて変わりません。
例えば、店頭金利が2.475%で優遇金利が2.0%で、適用金利0.475%で借りたとします。店頭金利が3.0%に上がった場合は、そのときの適用金利は、店頭金利3.0%-優遇金利2.0%=1.0%となるという具合です。
したがって、優遇金利が大きなときに住宅ローンを借りることができれば、返済期間全体を通して有利になります。
短プラ連動ではない変動金利もある
変動金利は短プラ連動と書きましたが、住宅ローンによっては短プラに連動しないものもあります。
商品説明や約款を見ると、金利決定の方法について書かれています。
例えばこちらはauじぶん銀行の住宅ローンの商品説明書。

auじぶん銀行の商品説明書
「市場金利をもとに独自で決定」とあります。
こちらは住信SBIネット銀行の住宅ローン約款。

住信SBIネット銀行の住宅ローン約款
「短プラが基準」と明記しています(以下の各号には、基準日や短プラが廃止された場合はそれに代わるものを基準にするなどと書かれています)。
銀行独自で定める金利は、銀行の経営状況などによって住宅ローンの金利を上げることが可能であることを意味し、短プラ連動よりもやや金利変動リスクが高いと言えます。
個人的には適用金利そのものや団信ほど重視しなくても良いとは思いますが、住宅ローンに迷った場合は金利の決定方法も確認してみてください。
返済期間
住宅ローンの返済期間は35年が一般的
ですが、35年にしなければいけないわけではありません。
30年にすることも可能ですし、住宅ローンによっては40年や50年といった返済期間を選択できるものもあります。

50年の住宅ローンもある(出典:西日本シティ銀行)
返済期間を延ばせば月々の返済金額は減りますが、借入残高も少しずつしか減少しません。
借入残高には金利が発生しますので、返済期間を長くすると総支払額は増えますので注意が必要です。
例えば、5,000万円の借入額を金利1.5%で返済する場合、返済期間35年の場合は返済総額6,430万円ですが、50年の場合は7,110万円と、同じ借入額と金利でも返済総額が700万円近く増加します。
また、ほとんどの住宅ローンは当初決めた月々の返済額よりも多く返済する繰り上げ返済が可能です。繰り上げ返済を利用することで、返済期間縮めることができ、金利負担を減らすことができます。繰り上げ返済には手数料が必要な場合もあるので、契約予定の住宅ローンの手数料を確認しておくことをオススメします。
返済期間が長いと返済総額が大きくなるデメリットがありますが、短ければいいというものでもありません。
返済期間を長くした場合、繰り上げ返済をすることで返済期間を短くすることは可能ですが、逆(短い返済期間を長くすること)はできません。
元利均等払いと元金均等払い
住宅ローンの返済方法には、「元利均等払い」と「元金均等払い」の2種類があります。
元利均等払い
元利均等払いは、月々の元金と金利負担の合計額が一定額になるようにする返済方法
です。
返済金額のうち当初は利息が多く、元金が少ないため、当初は元金返済額が少なく借入残高が減りにくくなっています。返済期間が進むにつれて、返済額のうち元金返済額の割合が増え、利息返済額が減っていきます。

元利均等払いの例(借入額:5,000万円 金利:0.5%)
元利均等払いは月々の返済額が一定であるため、収支計画が立てやすい点がメリットと言えますが、総返済額は元利均等払いのほうが多くなります。

ただし、変動金利の場合は、金利が変われば元利均等払いでも返済額が変わります。「返済額が一定」というのは、金利が変わらないことが前提です。
元金均等払い
元金均等払いは、元金返済額が一定になる返済方法
です。
元金に応じて金利負担分は変動するため、毎月の返済額は変動します。当初は元利均等払いに比べて返済金額が多くなりますが、元金を一定額で返済し続けるために、借入残高が元利均等払いに比べて早く減少します。
そのため、返済期間が進むにつれて、利息の支払いが少なくなり、総返済額は元利均等払いよりも少なくなります。

元金均等払いの例(借入額:5,000万円 金利:0.5%)
具体的には、借入額5,000万円で適用金利0.5%の場合、返済総額は元利均等払いでは5,451万円になりますが、元金均等払いでは5,438万円と13万円ほど安くなります。この差額は金利が高いほど大きくなります。
総返済額は元利均等払いよりも少なくなりますが、当初の負担が大きい点と、返済額が変動するので収支計画が立てにくい点がデメリットと言えます。
また、元金均等払いは元利均等払いよりも少し審査が厳しくなります(当初の月々の返済額が多いため)。
ボーナス払いを併用するかどうか
住宅ローンの返済では、ボーナス月は返済額を増額するボーナス併用払いを利用することができます。
ボーナス払いを併用することで、平常月の返済額の負担を減らすことができるのがメリットです。
とはいえ、ボーナスはあくまで会社の業績に連動する不確実なもののため、個人的にはボーナス払いに頼らなければ返済できないような返済計画はオススメできません。
特に変動金利の低金利を前提に考える場合は要注意です。金利が上昇するとあっという間に返済が苦しくなるリスクがあります。
例えば、4,000万円の借入残高で残り25年の返済期間の場合、金利0.5%では月々の返済額は約14万円ですが、金利3%では約19万円と、月々の返済額が5万円も増えます。
個人的にはボーナス払いに頼らない返済計画をオススメします。
手数料型と保証料型
住宅ローンを借りるにあたっては、「事務手数料」または「保証料」が必要です。
融資事務手数料
融資事務手数料とは、住宅ローンを借り入れる際に手続きの報酬として金融機関へ支払う費用のことです。
融資事務手数料は、「定率型」と「定額型」の2種類に分けられ、融資事務手数料型の住宅ローンを取り扱っている金融機関の多くは、定率型を採用しています(融資金額の2.2%が一般的)。
特にネット銀行はほとんどが融資事務手数料型です。

ちなみに楽天銀行は定額で33万円。
金利を考えなければ、1,500万円以上借り入れるなら楽天銀行の手数料は魅力的と言えます。
融資手数料は融資実行時に一括で支払う必要があります(諸費用として借入金額に含めることが出来る場合もあります)。
融資事務手数料を支払う場合は、保証料は原則不要です。
注意点として、融資事務手数料は繰り上げ返済(他行への借換含む)をしても戻ってきません。
保証料
保証料とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなったときに保証会社の保証を受けるために支払う費用です。
転職や退職など何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になった場合には、保証会社が銀行に対して住宅ローンの残債を支払います(ただし、債務者の負債が無くなるわけではなく、以降は保証会社に対して返済しなければなりません)。
なお、保証料型を選択した場合も、2~3万円程度の事務手数料が必要なこともあります。
保証料には、「一括前払い型」と「金利上乗せ型」の2種類が存在します。
保証料一括前払い型
一括前払い型は、住宅ローンの借り入れ時に保証料を一括で支払います。
メリットとしては、金利上乗せ方式よりもトータルで支払う保証料金額が少なくなります。
保証料は融資事務手数料とは異なり、途中で繰り上げ返済や一括返済した場合は戻ってきますが、同じタイミングで繰り上げ返済した場合、一括前払い型は金利上乗せ型よりも保証料の支払い額が多くなることがあるので注意が必要です。

たとえば、一部繰り上げ返済では保証料が戻ってこなかったり、一括繰り上げ返済の場合は事務手数料が差し引かれたりとか。

銀行によるので、契約書をよく確認してください。
また、保証料一括前払い型の場合、住宅ローン借り入れ時に保証料を一括で支払うため、まとまった資金が必要になります(融資金額に含めることができる場合もあります)。
保証料金利上乗せ型
金利上乗せ型は、保証料を住宅ローンの金利に上乗せして、毎月の返済に含めて支払う方式のことです。
住宅ローン借り入れ時に支払う費用が少なくなるといったメリットがある一方で、一括前払い型よりも保証料の総支払額が多くなる点がデメリットです。
繰り上げ返済した場合(借換した場合)、それ以降の保証料は支払う必要がなく、一括前払い型の返戻保証料よりも負担が少なくなることがあります。
保証料金利上乗せ型の場合は、ローン残高に対して0.2%のような形で保証料がかかります。一部繰り上げ返済でも、ローン残高が減るため、毎月の保証料負担も減ります。
一部繰上返済を計画している場合は、金利上乗せ型を検討するといいでしょう。
団体信用生命保険
住宅ローンの借入時には原則、「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入します(独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35では加入は任意)。
団信とは、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。

死んだ場合は住宅ローンの残高が0になる=返済が免除されるということ。
通常、住宅ローンには一般団信が基本付帯されています。つまり、住宅ローンの適用金利には、団信の保険料も含まれていることになります。
一般的な生命保険の場合は、基本的に年齢とともに病気のリスクは上がるので保険料は高くなります。しかし、団信の場合は、借入時の年齢や性別にかかわらず保険料(正確には金利に含まれているので金利負担)は一定です。
若い人からすれば金利には病気リスクに対して割高な保険料が含まれていると考えられますし、ある程度年齢を重ねた人であれば割安ということになります。
ただし、健康状態によっては団信に加入できない場合があります。その場合は、引受基準が緩和される代わりに金利上乗せが必要になる「ワイド団信」というものに加入する必要があります(ワイド団信も加入できない場合は民間の住宅ローンが利用できないため、団信加入が任意のフラット35しか選択肢がなくなります)。
また、団信は一般的な生命保険と異なり、加入期間中の見直しが出来ません。加入時点の保障内容は返済期間中変更できないので、慎重に検討・選択する必要があります。
団信で注意しておきたいのは、「保障内容」と「支払条件」です。
保障内容
団信には、債務者が死亡または高度障害になった場合に住宅ローン残高相当額が保険金として支払われることになっており、これを「一般団信」と呼び、全ての団信が備えています。
一般団信の保障内容は原則、死亡保障と高度障害保障のみ。通常、これらの状態以外の幅広い疾病リスクに対応するには、がん保障や3大疾病保障などの疾病団信に入る必要があり、保障内容に応じた金利上乗せが必要です。疾病団信は銀行によって上乗せ金利が異なりますので、疾病団信込みの適用金利で比較する必要があります。

たとえ適用金利が低くても、疾病団信の上乗せ金利が高いと意味がない…。
ただし、住宅ローンによってはこれら疾病団信が無料付帯する場合があります。
例えば、auじぶん銀行には、がんと診断されたら住宅ローン借入残高の50%が保険金として支払われるがん50%保障団信が付帯しています(金利上乗せ0.1%でがん100保障にすることも可能)。また、住信SBIネット銀行では、3大疾病保障50%、全疾病保障が無料付帯しています(40歳未満の場合)。

住信SBIネット銀行のスゴ団信(出典:住信SBIネット銀行)
これら疾病団信が無料付帯する場合は、充実した疾病団信の保険料が金利に含まれていると考えられるため、一般団信のみの住宅ローンと比べて「実質的な金利」は低いと言えます
。
無料で付帯する団信の保障内容および、疾病団信の上乗せ金利は必ず確認しましょう。
支払条件
保険金の支払条件についても確認が必要
です。
保障対象の疾病に罹患したとしても、支払条件を満たさなければ保険金は支払われません。
下記はじぶん銀行の団信の適用条件です。がんは診断のみで保険金が支払われますが、けが・病気では連続31日以上、その後継続入院180日が条件となっています(退院した場合、180日以内の再入院であれば継続入院として扱われます)。
しかし、現在180日もしくは連続31日も入院することはほぼありません。

35~64歳の平均入院日数は24.4日です(出典:公益財団法人生命保険文化センター)。
統合失調症等などでは入院日数は長くなっていますが、精神障害は保険金支払対象外(注釈に小さく書いてあります)。
これでは実質的に保障していないのと同じです。

病院側もそんなに長期間入院させていたら病床が足りなくなるからね。

auじぶん銀行の団信(出典:auじぶん銀行)
それに対して、住信SBIネット銀行の団信の全疾病保障の支払条件は「保障開始日以降に、特定疾病または重度慢性疾患により就業不能状態となり、その状態が継続し、就業不能状態」となっており、入院有無は問いません。

住信SBIネット銀行のスゴ団信(出典:住信SBIネット銀行)
団信は保障内容だけでなく、支払条件がどうなっているのかもしっかり確認しましょう。
単独ローン/ペアローン/収入合算
夫婦のうちどちらか1人しか収入がない場合(もしくは独身の場合)は自動的に単独ローンになりますが、共働きの場合は「ペアローン」または「収入合算」という選択肢が存在します(親子でペアローンを組む場合もあります)。
銀行によっては、ペアローンと収入合算の取り扱いがない場合や、どちらかにしか対応していない場合があります。
| ペアローン | 収入合算(連帯債務) | 収入合算(連帯保証) | |
| 住宅ローン | 夫・妻 | 夫 | 夫 |
| 連帯保証人 | 夫・妻 | – | 妻 |
| 連帯債務者 | – | 妻 | – |
| 団信 | 夫・妻 | 夫 | |
| 住宅ローン控除 | 夫・妻 | 夫 | |
ペアローン
ペアローンの場合、夫と妻がそれぞれ住宅ローンを1つずつ、計2つを契約することになります。
夫婦が同程度の収入の場合は、ペアローンがオススメです。メリットとしては、夫婦ともに住宅ローン控除が受けられ、団信にも加入できることです。
収入合算
同じ共働きで夫婦でも、妻がパートなど夫婦間の収入の差がある家庭は、収入合算という方法があります。
収入合算ではローンが1つで、収入が多い方を主債務者とし、もう一方を連帯保証人もしくは連帯債務者とします。
収入合算では、世帯収入として審査がされるので、単独ローンよりも借入額を多くできる可能性があるのがメリットです。ただし、団信には主債務者しか加入できない(ことが多い)点には注意が必要です。

団信に加入できない連帯債務者は、生命保険などでリスクに備える必要があります。
収入合算の方法には、連帯保証型と連帯債務型があります。連帯債務型を選択した場合は、夫婦ともに住宅ローン控除が受けられるのがメリットです。
収入合算に対応している銀行でも、取り扱っているのは連帯保証型のみという場合もあるので注意が必要です。
住宅ローンの諸費用
住宅ローンを借り入れる際は、前述した事務手数料や保証料に加えて、諸費用が必要です。
諸費用の代表的なものは以下の通りです。
- 印紙税
- 登記費用
- 火災保険料
印紙税
金銭消費貸借契約を書面での契約書を使って行う場合は、契約ごとに収入印紙が必要になります。
100万円超 500万円以下:2,000円
500万円超 1,000万円以下:10,000円
1,000万円超 5,000万円以下:20,000円
5,000万円超 1億円以下:60,000円
※ペアローンの場合は契約ごとに必要。
金銭消費貸借契約をWEBサイトで契約する場合は不要です。

ネット銀行では印紙代が不要。数万円ですが、節約することができます。
登記費用
また、土地・建物の購入や借換にあわせて、土地・建物に関する登記費用が必要です。
新規か借換か、新築か中古か、戸建てかマンションかで異なり、下記の通りになります(住信SBIネット銀行の解説ページが分かりやすかったので、順番を整理してそのまま掲載します)。
(※)で記載した登録免許税は、軽減措置により登録免許税の税率が変更になる場合があります。詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。
新築戸建を購入する場合・購入した土地に建築する場合(土地購入+建物新築)
| 抵当権設定費用 | 登録免許税 | 抵当権設定額(=借入額)の0.4% |
|---|---|---|
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
6~10万円程度 | |
| 所有権移転費用 | 登録免許税 | 土地評価額の2%(※) |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
~8万円程度 | |
| 所有権保存費用 | 登録免許税 | 建物評価額の0.4%(※) |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
3~6万円程度 |
自身の土地もしくは家族の土地に建築する場合
| 抵当権設定費用 | 登録免許税 | 抵当権設定額(=借入額)の0.4% |
|---|---|---|
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
6~10万円程度 | |
| 所有権保存費用 | 登録免許税 | 建物評価額の0.4%(※) |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
3~6万円程度 |
新築マンションを購入する場合
| 抵当権設定費用 | 登録免許税 | 抵当権設定額(=借入額)の0.4% |
|---|---|---|
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
6~10万円程度 | |
| 所有権保存費用 (土地の移転含む) |
登録免許税 | 土地評価額の2.0%、建物評価額の0.4%(※) |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
3~6万円程度 |
中古マンション・中古戸建を購入する場合
| 抵当権設定費用 | 登録免許税 | 抵当権設定額(=借入額)の0.4% |
|---|---|---|
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
6~10万円程度 | |
| 所有権移転費用 | 登録免許税 | 土地・建物評価額の2.0%(※) |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
~8万円程度 |
借換の場合
| 抵当権設定費用 | 登録免許税 | 抵当権設定額(=借入額)の0.4% |
|---|---|---|
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
6~10万円程度 | |
| 抵当権抹消費用 | 登録免許税 | 土地・建物各々1個あたり1千円 |
| 司法書士への報酬 登記に係る実費 |
設定済み抵当権の件数1件につき2万円程度 |
火災保険料
住宅ローンの借り入れの際には、一般的に火災保険への加入が義務付けられています。
長期間の住宅ローン返済中に仮に火災が起こってしまった場合、自宅に住めなくなる可能性があります。そうなった場合、住宅ローンの返済義務だけが残ることになります。契約者にとっては、住む家がなくなったり、新たに住む住宅を準備する費用も必要になったりするなど生活に困窮する可能性があり、貸し出しを行う銀行にとっては住宅ローンの返済が滞るリスクがあります。
そのため、住宅ローンを契約する際は、火災保険への加入が必須となっています。
ただし、火災保険は住宅ローンを借り入れる銀行から紹介される火災保険に加入する必要はなく、自分で好きな火災保険を選択することが可能です。ハウスメーカー提携の火災保険のほか、複数社の火災保険を比較検討して加入するのがオススメです。
火災保険についてはこちらの記事で詳しくまとめています。
【参考】みんなが選んだ住宅ローン
Twitterで、住宅ローンに関するアンケートを実施しました。
必ずしも「多数派が正解」というわけではない点に留意して、参考にしていただければと思います。
【アンケート】住宅ローンの金利タイプは何にしましたか?
ブログで紹介するかもしれません🙇— kikorist@住友林業の3階建て (@kikorist2020) April 20, 2023

やはり低金利を受けて変動金利が圧倒的ですが、北陸銀行は当初固定にすると0.1%台だったために当初固定にしたという方もいました。
【アンケート】繰上返済しますか?
選択肢4つまでのため、閲覧用の選択肢作れませんでした🙇
ブログで紹介するかもしれません🙇— kikorist@住友林業の3階建て (@kikorist2020) April 20, 2023

繰り上げ返済に関するアンケートでは、住宅ローン控除終了後に繰り上げ返済するという方と、繰り上げ返済しないという声が多い結果でした。

繰り上げ返済した場合は金利負担は少なくなりますが、団信の保険金も少なくなるというデメリットがあります。繰り上げ返済するデメリットも理解した上で選択するといいと思います。
【アンケート】住宅ローンの返済方法は、元利均等(毎月返済額が一定)と元金均等(毎月返済額が徐々に減少)、どちらを選択しましたか?
ブログでご紹介するかもしれません🙇— kikorist@住友林業の3階建て (@kikorist2020) April 20, 2023

元利均等が多いという結果に。低金利の場合は、元利均等と元金均等の差が少ないため、当初負担が低く返済計画も立てやすい元利均等が人気のようです。
FPによるライフプラン相談も有効
住宅ローンが借りられる金額と、返せる金額はイコールではありません
。

借りられる額を限度額まで借りるのはちょっと借りすぎだと思います…
住宅購入の予算設定にあたって役立つのが、FP(ファイナンシャルプランナー)によるライフプラン。収入や資産状況から無理のない住宅予算を導いてくれます。
私たちも住友林業との契約前に相談し、最近も子供が生まれたためにライフプランの見直しを行いました。
こちらの記事では、FP相談のポイントの解説と3社のFPのライフプラン資料の比較を行っています。

私たちを担当いただいてるFPのご紹介も可能です(相談料無料)。
私たちの担当FPについても記事で触れています。
本記事のまとめ
本記事では、住宅ローンの借り入れを検討している方向けに、知っておきたい住宅ローンの基礎知識についてまとめました。
住宅ローンには様々な選択肢がありますが、どれがベストかは一概には言えません。個々人の経済状況や将来に対する考え方、リスクの許容度などで、正解は変わります。
重要なことは、選択肢それぞれのメリット/デメリットを把握し、どの選択肢が自分たちにあっているかしっかり検討することです。
本記事を読んでいただき、ご自身のベストな選択肢を見つけていただけたら幸いです。

なお、私たちの住宅ローン戦略については別記事で解説してます。
これから住宅ローンを検討する方は、我々の住宅ローン戦略も考え方の1つとして参考にしてみてください。
また、本記事で紹介した「モゲチェック 住宅ローン診断」も活用してみてください。

参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。



























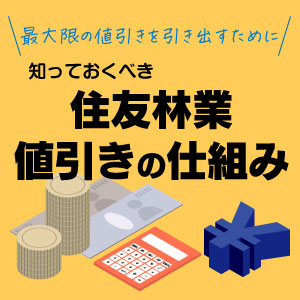














コメント