当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
注文住宅を検討する中で、先輩施主ブログやTwitterでの情報収集(#家系ブログを盛り上げる会)と並んで最も役に立ったと言っても過言ではないのが、メガソフトが販売する3D住宅デザインソフトのマイホームデザイナー。

間取りの検討段階から、クロスなどの内装検討に至るまで大活躍!超優秀ソフトです。
しかも、後述するようにマイホームデザイナーで作成したパースの再限度は完璧。
基本的な操作は誰でもできて、さらに慣れてくれば高度が使い方もできるという、懐の深いソフトとなっています。
本記事ではマイホームデザイナーがkikorist夫婦の実際の家づくりにどのように役立ったのかまとめます。
また、マイホームデザイナー14のメリット/デメリットのほか、オススメ出来る人や出来ない人についてもまとめています。

バリバリ使い倒している施主目線で解説します。
3Dマイホームデザイナーとは?
3Dマイホームデザイナーとは、メガソフトが開発・販売する注文住宅設計用のソフトです。
メガソフトは3DマイホームデザイナーPROという、プロの建築士や工務店が業務レベルで使う設計ソフトも販売していますが、3Dマイホームデザイナー(現在の最新バージョンは14)は業務用ソフトから高層建築などの専門的な機能を削り落として価格を抑えた一般施主向けソフトという位置づけです。
一般の施主向けソフトとしては十分すぎる機能があります。
マイホームデザイナーの主な機能は下記の通りです。
- 間取りの設計
- 立体化(パースの作成)
- 内装/外観のデザイン検討
- 家具・照明の配置・検証
①間取りの設計
マイホームデザイナーの間取り作成は、間取りパレットから該当するパーツを選んで配置するだけで完成します。
グリッドも、住友林業などで採用されている尺モジュール(1マス91cm)、積水ハウスなどのメーターモジュール(1マス100cm)のどちらにも対応可能です。

部屋の頂点を編集することで、四角形ではない多角形や、R壁なども作成することができます。
建具や窓なども配置できます。
②立体化(パースの作成)
作成した間取りは、ボタン1つで立体化して、パースとして確認することが出来ます。
天井高も設定可能ですし、屋根形状も寄棟、片流れ、切妻、陸屋根などが選べ、屋根の形は矩形から自動的に設定されます(軒の出なども調整可能)。
立体化後は、外観・内観ともに好きな場所からパースを確認することが出来ます。

③内装/外観のデザイン検討
床や壁紙、キッチンなど住宅設備はテクスチャを選べるだけでなく、模様の倍率変更や回転も可能です。
無料で利用できるテクスチャが豊富にあるだけでなく、画像データ読み込ませてテクスチャとして設定することもできるので、壁紙メーカーなどが公開しているテクスチャ画像を使えば思い通りの内装にすることができます。
④家具・照明の配置・検証
マイホームデザイナー14ではパース上に家具や家電、照明などを自由に配置することが可能です。
マイホームデザイナーを購入すると、半年間は無料で5万点以上の実在メーカーの家具・住宅設備・テクスチャなどをダウンロード可能がデータセンターが利用できるのですが、これが本当に便利(半年経過後はダウンロード済みパーツはそのまま継続して利用可能。新規ダウンロードは3か月3,000円の有料会員登録が必要)。

データセンターには柏木工やマスターウォールなどの有名家具メーカーの家具もありました。
配置するパーツのサイズや色を変更することも可能ですので、購入予定の家具をサイズ調整し、間取りに配置してみて大きさなどが問題ないか確認することが可能です。

マイホームデザイナーはどこで買える?
パッケージ版はヨドバシカメラやビックカメラなどの大型家電量販店のPCソフト売り場でも販売されていますが、オススメなのは楽天市場とAmazonです。
最近はPCソフトもオンライン販売やサブスクが主流なので、ヨドバシなどのPCソフト売り場はどんどん縮小されています。ネット通販なら翌日に届きますし、ネット通販はパッケージ版はもちろん、ダウンロード版も選択できます。時間を優先するなら即使えるダウンロード版がいいでしょう。
マイホームデザイナーには、ソフト単品、ガイドブック付き、住空間セットの3種類があります。
このうち住空間セットは家庭科で使用する教材向け商品ですので、一般施主は選ぶ必要はありません。パソコンが苦手な方には、ガイドブック付きがオススメです。

マイホームデザイナーはメガソフトの中の人がYoutubeで解説動画を用意してくれていたりするので、私はガイド本なしでも大丈夫でした。
マイホームデザイナーの再現度は?
ハウスメーカーである住友林業が作ったパースと、素人である私たちがマイホームデザイナーで作ったパースを比較してみます。
マイホームデザイナーの外観の再現度チェック
まずは住友林業が作成したパース。

こちらがマイホームデザイナーで作成したパース。

住友林業が作成したパースとほぼ同じものが出来上がりました。
3階のバルコニーとアプローチ周りのタイルは、マイホームデザイナーのデザインが実際の建物を反映しています(住友林業が作成したパースは検討中にもらったもののため、デザインが古い)。
素人が作ったとは思えない再現度です。
マイホームデザイナーの内装の再現度チェック
まずは住友林業が作成したパース。

こちらがマイホームデザイナーで作成したパース。

内装も住友林業が作ったパースとほぼ同じものがマイホームデザイナーで出来上がりました。住友林業が作成したパースはテレビ背面がウッドタイルですが、実際はエコカラットに変更しています。
違う方向からの住友林業のパース。

続いてマイホームデザイナーで作成したパース

これもほぼ同じものが出来上がりました。奥の窓は実際には掃き出し窓に変更し、トールスピーカーやフロートタイプの造作テレビボード、ソファの形状、天井のスピーカーやダウンライトなどはマイホームデザイナーのほうが再現度が高いくらいです。

これだけのものが再現できるのはスゴイ!!

しかも、自分たちで視点を自由に変えられるし、素材なども好きに変更できるから最高だよね。
マイホームデザイナーの再現度はほぼ完璧
以上のように、マイホームデザイナーはほぼ完璧にハウスメーカーの図面と建築パースを再現可能です。
窓や建具のサイズや配置もミリ単位で変更できます。図面に記載されている窓のサイズと高さを入力するだけで同じものができます。窓枠の色も内側と外側で好きなように変更できます。

先週打合せ時にはPCを持ち込んで、マイホームデザイナーで私が作ったパースを設計担当氏や営業担当氏に見せましたが(クロスのイメージを伝えるため)、住友林業の社員にも驚かれるほどの再現度でした。

住友林業ではパースは専門の3Dチームに依頼して作成しているのですが、遜色ないですね。
実際に完成した注文住宅と比較してみた
実際に計画していた家が完成したので、こちらの記事でマイホームデザイナーのパースと実際の家を比較しています。
詳細は記事をご覧いただきたいのですが、マイホームデザイナーで作成したパースと実際のリビングの写真を比較してみます。


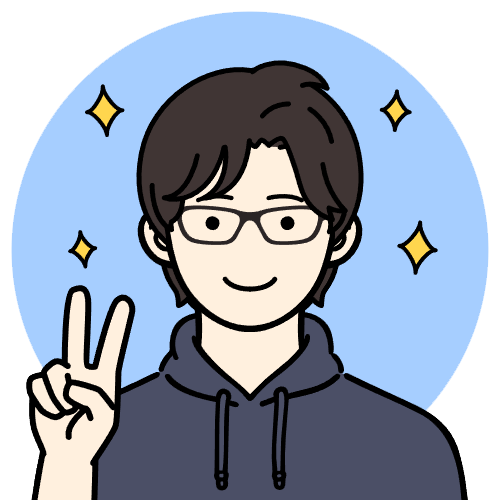
結論、パース通りの家が完成しました!

同じ図面から作成したパースと家が同じというのはある意味当たり前ですが、この再現度です。
マイホームデザイナーのメリット
マイホームデザイナーのメリットは下記の通り。
- 失敗を回避できる(可能性が高い)
- 間取りを自分たちで検討できる
- 内装を自分たちで検討できる
- 家具・家電のサイズ検討に使える
①失敗を回避できる(可能性が高い)
誰しも一生に一度のマイホームで失敗はしたくないものです。
マイホームデザイナーを使うことで、間取りや内装で失敗した…ということを可能な限り回避できます。

あくまで、「失敗を避けられる」という点が重要です。いい間取りになるかは、営業担当氏や設計士次第です。
もちろん、マイホームデザイナーを使わなくてもいい家を作ることは可能ですし、作っている方は大勢います。しかし、ソフトを使ったからと言って、ダメな家になるということは一切ありません。

自分で作った間取りが正しいと思ってプロの意見を無視するようになったらヤバいと思いますが…
使うことのメリットはあっても、デメリットはありません。
マイホームデザイナーの優れた点は、間取りから立体化して、視点を動かしながら確認ができる点です。立体で視覚化することで、平面では気づかなった点に気づくことができます。
例えば、私たちは1階階段背面をエコカラットにしていますが、エコカラットから壁紙に切り替わる1階と2階の切り替え部分には気づいていませんでした。
マイホームデザイナーを使うことで、その切り替え部分に気づくことが出来ました。
こうした点を事前にシミュレーションできるかどうかは重要です。


また、造り付けの造作家具についても立体的に検討できました。
当初案では、リビングの学習スペースには右端に90cmの収納キャビネットが来ていましたが、90cmでは収納もデスクも使いにくいとなり、90cmの収納を45cmの収納2つに分割することにしました。

キャビネットを45cmに分割した場合、①中央と右端、②左右両端という2案がありましたが、それぞれパースで検討できました。



比較すると左右に置いたほうがバランスいいね。
これが平面図だと、どちらがいいのか分かりにくいのです。
人間は自分にとって都合のいい情報を選択しがち、根拠なく自分だけは大丈夫と思いがち、になる「正常性バイアス」という特徴を持っています。立体的なパースを見ることで、正常性バイアスの影響で誤った判断をすることを回避できます。
②間取りを自分たちで検討できる
間取りはプロである設計担当にお任せすることが基本です。
マイホームデザイナーがあっても、設計担当と同じ仕事ができるわけではありません。構造や法規制、採光など専門知識がなければ実際の家の間取りは作れないからです。
また、経験の面においてもプロの設計担当には敵うはずがありません。
ただし、マイホームデザイナーを使うことで、自分たちで設計担当が作った間取りのチェックや改良をすることが可能です。あくまでベースは設計担当が作った間取りですが、そこからより自分たちの好みに近付けることは可能というわけです。
私たちは実際に、マイホームデザイナーで住友林業の間取りをベースに自分たちでいじることで、脱衣所の隣にファミリークローゼットを作ったり、1階のトイレ周りのレイアウト案の検討ができました。



自分たちでの間取りの検討は方眼紙に手書きしてもできなくはないですが、やはりソフト上で出来たほうがはるかに簡単です。何よりちょっとした変更や修正が簡単。
③内装を自分たちで検討できる
打合せが終盤になると始まる床材やクロス選び。合うと思っていたアクセントクロスとベースクロスが実際に組み合わせるとちぐはぐだったり、失敗を恐れて無難なクロスを選びがちです。
でも、マイホームデザイナーがあればクロスの色の組み合わせを自由にシミュレーションすることが可能です。
例えば、子供部屋になる予定の3階居室の広い面をアクセントとして青にしてみましたが、これもマイホームデザイナーでシミュレーションして問題なさそう、という感覚を打ち合わせ前に掴むことができました。

④家具・家電のサイズ検討に使える
マイホームデザイナーには、ソファやテレビ、観葉植物や収納棚などの様々な家具が登録されています。
実際の間取りに配置することで、家具の大きさやテレビとソファの間隔、通路の幅を確認することができました。


家具屋の広い空間で見るのと、実際の部屋で見るのとではかなり違いがありますので、パース上でサイズを確認できるのは非常に便利です。
マイホームデザイナーのデメリット
そんな便利なマイホームデザイナーですが、デメリット…というか欠点もあります。
- 有料ソフト=費用がかかる
- スキップフロアや折り上げ天井は工夫する必要あり
- Windows PCのみの対応
- 徹底するならスキルと時間がある程度必要
①有料ソフト=費用がかかる
マイホームデザイナーは有料ソフトです。ソフト単体で13,827円です(2024年6月現在のAmazonでの販売価格)。1回しか建てない注文住宅のために買うのはもったいない、と思う方もいるかもしれません。
…が、その分再現度は抜群に高いですし、家具・設備データも無料でしかも5万点以上と豊富です。有名メーカーの設備や家具はたいてい入っています。間取りや建具、開口部など細かい設定ができるので、本当に実際の家の通りのパースを作ることが出来ます。
マイホームという数千万円の買い物において、失敗の回避やより良い改善を、わずか1万数千円のソフトでできるなら、とんでもなくコスパがいいのではないでしょうか。
間取りの検討から内装・外観・外構・家具の検討にまで使えるので、「買って損はなし」と言い切れます。
マイホームが建ったあとは、メルカリなどでソフトを売却してしまえば(自分のPCからアンインストールするなどライセンスの扱いにご注意ください)、投資した分もある程度回収が可能です。
②スキップフロアや折り上げ天井は工夫する必要あり
最近流行りのスキップフロアや、ピットリビング、折り上げ天井は無印だとそのままでは作れません(Proソフトなら可能)。
…が、工夫すれば再現することが可能です。メガソフト自ら対処方法を公開しているのでデメリットとまでは言えませんが、スキップフロアや折り上げ天井は一般的になっている造りなので、無印でも対応してくれたらいいのに、とは思います。
③Windows PCのみの対応
マイホームデザイナーは、Windows PCのみの対応です。残念ながら、マイホームデザイナーはMacには対応していないため、Macユーザーは新たにWindowsPCが必要です。
個人的にはWindowsPCをマイホームデザイナーのためだけに購入するのもアリだと思えるほど、有益なソフトだと思っています。
必要なPCスペックも決して高くないので、マイホームデザイナー専用に安いWindows PCを導入するのもアリです。
④徹底するならスキルと時間がある程度必要
マイホームデザイナーはハウスメーカーが作るパースに対して95%の完成度であれば誰でも短時間で作成可能です。しかし、残りの5%まで似せようと思った場合は、テクスチャを使いこなしたり、自分で壁や棚を作ったりなど、それなりのスキルや見た目を追い込む時間が必要です。

したがって、焦って着工合意直前に買っても、細かい部分のチェック…というのは難しいと思います。
買うのであれば、家づくりの打ち合わせを本格的に始めるタイミングが理想ですが、内装の打ち合わせ中でも遅くはないと思います。

クロスなどは最後まで変更できますので、じっくり家で検討したい人は購入がオススメです。
どうしてもマイホームデザイナーが使いこなせないということであれば、私が代理でデータを作成することも可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

私が作成したデータを受け取って、自分のマイホームデザイナーで読み込めば、好きなようにパースが確認できるようになります。
マイホームデザイナーをオススメしたい人
以上を踏まえてマイホームデザイナーをオススメしたい人はこんな人です。
- 自分で間取りを修正したり、内装チェックをしたい
- お金をかけても失敗は可能な限り避けたい
とにかく自分たちで入念に検討したい、絶対に失敗したくない方には非常にオススメできます。
マイホームデザイナーをオススメできない人
逆にマイホームデザイナーをオススメできない人はこんな人です。
- PCが苦手
- お金と時間をかけたくない
やはりネックになるのは、PCのスキルでしょうか…。
95%似せるだけなら簡単で誰でもできますが、そこから機能を使い倒して、100%似せるにはある程度PCスキルが必要です。

正直どこまでこだわるか…。
マイホームデザイナーのデータ作成代行
マイホームデザイナーを使ってパースを確認してみたいけど、難しそう…という方のために、ココナラにマイホームデザイナー作成代行のサービスを出品しました。

ご依頼いただければ、私が全力で作成します!
マイホームデザイナーの作成で行き詰っている方で、ちょっとお願いしてみようかなという方がいらっしゃいましたら、ココナラから依頼を頂ければと思います。
料金などの詳細はこちらをご覧ください。
詳細版をココナラで確認
未登録の方は紹介コードの入力で1,000円引きになります。
本記事のまとめ
ハウスメーカーが資料で作るパースは数点のみで、しかも毎回の打ち合わせで用意されているわけではありません。
しかし、マイホームデザイナーがあればハウスメーカーと同じ精度で、自宅でいつでも自分で好きな角度・場所で家の中・家の外を確認することが可能です。
立体的かつ視覚的に確認できる便利さは想像以上です。


マイホームデザイナーは大活躍で、購入して本当に良かったと思っています。
マイホームデザイナーのおかげで多くのおうち時間を間取りの検討や内装の検討にあてることができました。
この記事を見てちょっとでもいいなと思った方にはマイホームを検討しているなら絶対にオススメしたいソフトです。
参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。







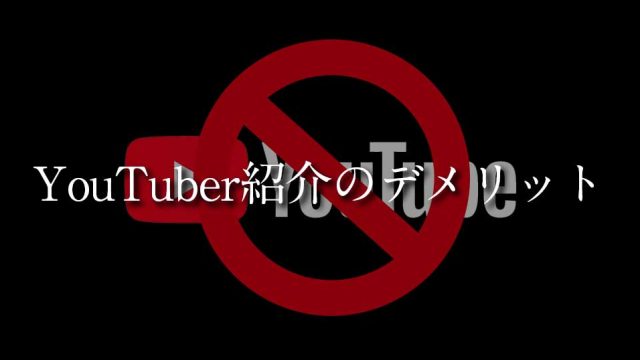



















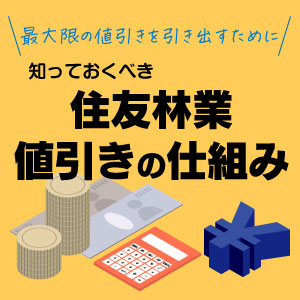














コメント