当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
注文住宅を考える際、言うまでもなく予算設定は非常に重要です。そして、注文住宅の予算設定を検討する上で必要なのが「ライフプラン」です。
ライフプランとは、個人や家庭が将来にわたってどのように生きていきたいかを具体的に描き、そのために必要な人生の各ステージで必要となる資金を計画することです。その中には住宅に関する費用も当然含まれます。
ライフプランの検討で役に立つのが、資産運用や保険、税金・相続対策など専門知識を持つファイナンシャルプランナー(以下、FP)への相談です。
私たちは注文住宅を契約する際、FPに相談を申し込み、ライフプランの分析を依頼していました。それから4年が経過し、新たに子供も2人生まれたことで、改めてライフプランの分析と保険の検討をするためにFP相談を行いました。
本記事では、私たちが実際に体験した結果・資料をもとに、FPを選ぶ際のポイントや相談の流れについて詳しく解説します。

資料を比較してもらうために、ありのままを紹介します!
今回、(4年前と同じFPを含む)3社のFPにライフプランの作成を依頼し、必要な資産運用や保険について相談。4年前に相談した担当FPのライフプラン分析・提案が最も信頼できるという結論になりました。
ブログで紹介することの快諾を得ていますので、信頼できるFPをお探しの方には私たちの担当FPのご紹介も可能です(本記事の最後に詳細をまとめています)。
ライフプランとは?ライフプラン作成のメリット
ライフプランとは?
ライフプランとは、個人や家庭が将来にわたってどのように生きていきたいかを具体的に描き、そのために必要な人生の各ステージで必要となる資金を計画することです。
ライフプランの作成にあたっては、ライフイベントを計画し、収入・資産・費用からキャッシュフロー表を作成します。

ライフイベントとは、結婚・出産・マイホームの購入やメンテナンス・子供の進学・車の買い替えなどを年表形式にしたものです。
ライフイベント表
こちらが担当FPが我が家のライフイベントをヒアリングいただいて完成したライフイベント表です。

本記事では資料画像をタップもしくはクリックすると拡大できます。
見にくい場合は、画像をタップ(クリック)してみてください。


子供の進学は小・中・高・大、それぞれで国公立なのか、私立(文系・理系)なのか、留学させるのか、下宿を想定するのか、習い事はどうするのか、子供の結婚祝いなどを出すのか、車は何年ごとにいくらの車にするのかなど細かくヒアリングされます。
キャッシュフロー表
収入と支出、資産、加入している年金・保険に、ライフイベントでの支出を加味してキャッシュフロー表が作成されます。
こちらが我が家のキャッシュフロー表です。


「ご本人様(夫)」の年収が52歳まで2,000万近くありますが、これは最近始めた生前贈与の影響ですね…(チートですみません)。収入の実力値は53歳以上の部分です。

第3子に伴い、「配偶者(妻)」は育休のため1年は給与収入が0になります。
育児休業給付金との差を「その他支出」の項目で調整しています。
収入から支出を差し引くと、残りが貯蓄になります。
キャッシュフロー表は、基本的に在職中は収入>支出になりますが、退職したり、子供が大学入学などで支出が増えると、収入<支出となり、不足分は資産を取り崩して生活することになります。
何歳まで生きるのかは不明ですが、「人生100年時代」というように、100歳まで資産が枯渇しなければひとまず安心と言えると思います。
もし、資産が枯渇するのであれば、収入または支出、あるいは資産運用を見直す必要があるということです。
キャッシュフロー表を作ることで、いくらまでなら住宅予算をかけても問題ないかが明らかになります。生活費や車などの必要経費、老後資金、教育資金を確保した上で、余る予算が住宅にかけられる予算(維持費を含む)ということになります。
ライフプラン作成のメリット
ライフプランを作成するメリットは大きく2つです。
- 必要な資金の可視化:希望する人生に必要な資金を可視化することができ、収入・資産の充足状況や不足額を可視化できる。
- リスク管理:予期しないリスクに対して備えることができる(例:失業、病気、死亡など)
メリット①:必要な資金の可視化
ライフプランを作成するメリットとして、住宅資金・教育資金・老後資金という人生の三大資金の可視化があります。
住宅の予算はいくらまでかけられるのか、固定資産税や地震/火災保険といった維持費、修繕費用、子供の進学先をどうするか、老後に今の生活水準を維持することができるかなど、人生に必要な費用を計算し、収入・資産の充足状況や不足額を可視化することができます。
充足していれば安心することができ、不足していれば何らかの対策が必要です。
メリット②:リスク管理
ライフプランを作成することで、人生の途中で失業、病気、死亡などによって収入が途絶えた際に、どういった準備・金額が必要なのかも明らかにすることができます。

この万が一の準備は、保険を想像しがちですが、保険だけではなく貯蓄・資産運用、相続対策なども含みます。
ライフプランの作成方法は?オススメはFPへの作成依頼
ライフプランは、自分でもExcelなどを使って作成することはできますが、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持った専門家に作成してもらうことをオススメします。
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、FP技能検定(1~3級)・AFP・CFPといった資格を保有し、家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、将来の夢がかなうようにサポートする専門家です。

ライフプランの作成は単純に手間ですし、やはりプロに任せた方がミスがなく安心。

在職中はまだしも、厚生年金・企業年金、個人年金保険、相続などが絡むと複雑に…。
FPは一般的にライフプラン設計のための専用ソフトを使用するため、資料が分かりやすいというメリットもあります(自前でExcelで作成しているFPもいます)。

ただし、専用ソフトであっても資料の分かりやすさや細かさは異なる上、物価上昇を加味するかなど入力内容もFPによって異なるので注意が必要です。

本記事の後半では実際に3社のFPに作成してもらった資料を比較しています。
ファイナンシャルプランナー(FP)の選び方
FPには、相談料が有料のFPと、相談料が無料のFPがあります。
個人的には有料相談のFPを選ぶメリットは少なく、無料相談のFPで十分と考えます。その理由について、以下でそれぞれの特徴を見ながら解説します。
有料のFP相談
有料のFPは相談自体から対価を得ており、相談料は1時間ごとに発生する料金体系が一般的です。
日本FP協会のウェブサイトで相談できるCFPを検索できます(検索できるFPには相談料無料のFPもいます)。
有料FPの相談料は、1時間あたり3,000円~2万円超えまでと幅広い相談料が設定されています。ここで問題なのは、相談料はFPが自由に設定しているため、相談料の高低に対する合理的な理由が見当たらない、ということです。

高額だからといって必ずしも良いFPとは限りませんし、安いからといって質が低いとも限りません。
こちらは上記ページから検索結果に表示された22,000円/時間のFPのプロフィールですが、この説明で良いか悪いかなんて判断できる人はまずいないと思います(この方が悪いと言っているわけではありません、念のため)。


ちなみにプロフィールの下の業務経験や経歴、FPのホームページに飛んでも、全くどんなアウトプットが得られるのか全く分かりませんでした…。
FP相談ではライフプラン分析の資料や提案内容が重要なのに、ほとんどのFPでそのアウトプットが全く見えない。ふわっとした印象論の説明があるだけ。

だからこそ、この記事では私たちが体験したFPの資料や内容を比較のため掲載しています。
個人的には、アウトプットが分からないのに有料で相談するのはお金の無駄と考えます。

商品が分からないのに購入なんてできないですよね。
唯一意味があるとすれば、知人などの紹介により、そのFPに相談料を出す価値があると分かっている場合です。バイネームで指名できない限りは、有料のFP相談を使う必要はないというのが私たちの考えです。
有料FPを利用する明確なメリットが正直ありません。
無料のFP相談
無料のFPは、彼らが提案する保険や証券会社からの手数料が収入源となっています。
相談料を無料にすることで相談のハードルを下げ、間口を広く狙うビジネスモデルと言えます。
提案される保険の加入や証券口座の開設/証券購入はあくまで任意です。話を聞いて、必要性があると思えば加入・開設すればいいですし、不要だと思えば加入する必要はありません。そして保険加入や証券購入がない場合も相談料は発生しません。あくまで相談者の課題を解決する良い提案をしなければFPの収入にはならないということです。
同じ保険であればFPの保険提案経由で保険に加入しても保険料が高くなることはないので、その点は安心してください。

私たちが加入したFWD生命の収入保障保険のように、代理店・募集人経由でしか加入できない保険もあります。
また、有料のFP相談でも保険や証券等の提案を行いますので、無料のFP相談だけが保険提案があるわけではありません(もちろん相談者の必要性に応じてですが、この点は無料FPも同様です)。

有料のFP相談は、相談料と保険手数料の二重取りしているとも言えます(ビジネスモデルの違いですので、それが悪いわけではありません)。
このように見てみると、無料相談のFPを利用するデメリットは一切なく、むしろ相談料が無料である分コストパフォーマンスは高いのではないでしょうか。
したがって、私たちはFP相談するなら無料で十分と考えています。
ハウスメーカーの紹介のFPには要注意
住宅検討時に、ハウスメーカーや不動産業者からFPへのライフプラン相談を提案される場合があります(基本的に無料)。
こういったハウスメーカー経由のFP相談の場合、ハウスメーカーに都合の悪いことは言わないようFPが言い含められていることがあるので、注意が必要です。
FPの立場からすれば、ハウスメーカーは顧客を紹介してくれる存在です(多くの場合両者の間で金銭的なやり取りもあります)。そのため、FPは「このハウスメーカーは予算的にはやめておいたほうがいい」というようなハウスメーカーに都合の悪いことは言いにくい傾向にあります。

ハウスメーカーからすれば、「自社で建てても予算的に大丈夫」と言ってくれるFPが有り難いですよね。
ハウスメーカーとFPの間にはこのような利害関係があるため、住宅予算をそのハウスメーカーにあう形で過大に提案される可能性がなきにしもあらず、というわけです。
ハウスメーカー紹介のFPは信用してはいけない、とまでには言いませんが、上記のようなバイアスがかかっている可能性があるという点は頭に入れておきましょう。
FP相談の流れ
FP相談は有料・無料ともに、概ね2~3回に分けて行われます。1回あたりの所要時間は60分が目安です。
- 1回目家計状況・ライフイベントのヒアリング
月々の収入と支出、貯蓄額や資産運用の内容、ライフイベントについてヒアリングがあります。
- 2回目ライフプラン分析
1回目の面談でヒアリングした内容を元にFPがライフプランを作成。完成したライフプランについて説明を受けます。ライフプランに課題があるようであれば、その課題についても説明があります。
- 3回目
(2回目)課題解決提案ライフプラン上の課題に対して、解決策の提示があります。解決策は、保険提案以外にも資産運用、住宅ローンの借換、節税対策など相談者の課題に応じて多岐に渡ります(2回目の面談で提案がある場合もあります)。
無料FPの相談結果・資料の比較
私たちが今回相談したのはいずれも相談料無料のFP。
相談したのは、リクルートが運営する保険チャンネル、FPパートナーが運営するマネードクター、そして最後が私たちが家を建てる際に相談したカスタマーリンクスの担当者です。

気に入っているなら最初からカスタマーリンクスの当時の担当FPに相談すればよかったんですが、ほかにも色々説明を聞いて比較してみたくて…。

そして結局ふりだしに戻って来るという。
保険チャンネル
保険チャンネルは、リクルートが運営するFPへの無料相談ができるサイト。サービス名は「保険」チャンネルですが、無料FPへの相談がメインのサービスです。

相談できるFPは、保険チャンネル(リクルート)所属の社員ではなく独立FP、もしくはFP会社に所属するFPです(つまり保険チャンネルは、SUUMOなどと同じプラットフォームの提供)。相談内容を選ぶと、それに応じたFPが担当として付きます。

大手リクルートが運営するサービスのため登録しているFPが多いのが特徴ですが、保険チャンネルに所属しているわけではないので、使っているライフプラン作成ソフトやスキルがFPによって全く異なります。
また、相談内容からFPが紹介される方法以外に、プロフィールを見てFPを選ぶこともできますが、プロフィールだけでは良し悪しが分からないのはFP協会の検索機能と同じです。
私たちが保険チャンネルで紹介されたFPは東京海上日動あんしん生命保険のソフトを使っていましたが、正直分かりにくかったです…。
また、物価上昇率を加味していない、資産運用の利回りを0%で置くなど、ちょっと大丈夫か?という感じでした…。


もしかして外れだったのかもしれない…。
キャッシュフロー表
そもそも「縦」っていうのが見にくいんですよね…。

年度別収支グラフ
これもイマイチで分かりにくいです。

金融資産残高グラフ
運用利回りを全く考慮していないため、タンス預金と同じ。貯蓄額が積み上がっているのみです。

ライフプランの課題と提案内容
保険チャンネルのFPの診断は、私たちは十分な収入と資産があるため、結果として保険は不要という結論でした。

このライフプランで信じていいのかと言われると不安しか…。
強いて言えばということで、FWD生命の収入保障保険となないろ生命のなないろスリーというがん保険を提案されましたが、そもそものライフプランの精度がイマイチで、FWD生命の収入保障保険も私たちの想定内、がん保険に至ってはそもそも不要と考えていたので加入はお断りしました。
マネードクター
マネードクターは大手保険乗合代理店(=複数の保険会社を扱う代理店)のFPパートナー社が提供するサービス。KAT-TUNのCMでご存知の方も多いと思います。

保険チャンネルと異なり、相談できるFPは、全員がFPパートナー社に所属している社員です。
そのため、使っているライフプラン作成ソフトもマネードクターの独自の分かりやすいソフトで統一されており、大手ということもあってFP個人間のスキルなどの差も少ない印象です。
きちんと遺産の運用利回りも設定してくれていましたが、一律3%でした。

個人的には次で紹介するカスタマーリンクスの精緻な資料のほうが好みでしたが、マネードクター資料は簡潔で非常に分かりやすいので、マネードクターが好みという人も多そうです。
キャッシュフロー表
本人収入・配偶者収入は手取り計算になっているのかな?それでも低い気がしますが…。

贈与などは、暦年ではなく一部初年度に計上し、その後もその他収入で形状しているようです。

教育費診断
マネードクターの資料には、キャッシュフローグラフはありませんでしたが、他社にはない教育費診断という教育費のみをグラフ化した資料がついているのが特徴的でした。


毎年の教育費の金額推移やいつ頃がピークなのか視覚的に把握しやすい。
住宅ローン診断(資産残高グラフ)
保険チャンネルの時と違って、マネードクターでは第3子まで想定してライフプランを作成してもらいました。
そのため教育費が増えていますが、金融資産の運用利回りを設定しているために預貯金残高(=資産残高)は100歳時点で約8億と右肩上がりのグラフになっています。
資産残高が生涯マイナスにならなければ大丈夫と言うことになります。

ライフプランの課題と提案内容
ライフプランの診断はマネードクターでも問題なしとの回答。自分たちの金融資産で問題なく対応できるため、働けなくなった場合の保険も不要とのことです。
そこで提案いただいたのが、メットライフ生命のビーウィズユープラスⅡという外貨建ての保険です。ビーウィズユープラスⅡは最初にドルで一時払いをする生命保険で、「被保険者の死亡時の生命保険金非課税枠を利用した将来の相続対策として有効」ということで提案いただきました。
しかしながら、現在の歴史的円安状況に加えて、外貨建て一時金払いは運用利回りは自分でインデックス投資した場合に大きく劣る(=保険会社の取り分が大きい)ことから加入は見送りました。

提案された保険商品は類似商品と比べて優れているかどうか、保険料が安いか、本当に必要かなどを吟味する必要があります。
FPパートナー社と生保各社の不適切な関係に関する報道について
週刊東洋経済や週間ダイヤモンドといった経済誌で、マネードクターを運営するFPパートナー社と生保各社の不適切な関係が報道されています。



報道の内容を要約すると、生命保険各社から見込み顧客紹介や採用者の紹介、広告費という名目で便宜供与を受けており、これら便宜供与を行う生命保険会社の保険勧誘を優遇しているのではないかというものです。
FPパートナーの内部資料によると、アフラックから年間9000万円超、ひまわり生命から6000万円を、広告料として過年度に受け取っている。FPパートナーが運営する、マネードクターのウェブサイトと店舗(5月末で27店舗)のサイネージボードに掲載する広告の料金というが、はたして相場に見合ったものなのか。
(中略)FPパートナーが、そうした生保からの各種支援実績を踏まえて、顧客に推奨する保険を決めているとすれば、顧客本位とは程遠い。1億円近い広告費を払っているアフラックの保険を販売すると、FPパートナーの社内表彰上の評価において、獲得保険料が「3倍でカウントされるようになっている」(FPパートナー関係者)。アフラックの保険を強力に勧める動機づけになっているようだ。
「生保業界のビッグモーター」にすり寄る生保 生保による過剰な便宜供与と利益供与が復活(東洋経済オンライン)
複数の保険会社を扱う保険代理店を「乗り合い代理店」と呼びます。乗り合い代理店では、複数の保険から顧客が最適なものを選べるのではなく、顧客に不利・不要な内容であっても代理店の都合で勧奨することはありえるのだろうなと思います。
相談者には保険商品の知識が少ない(そもそも保険会社や商品が多すぎる…)ため、FPや代理店に言われるがまま入りがちです。繰り返しですが、提案された保険商品は類似商品と比べて優れているかどうか、保険料が安いか、本当に必要かなどを相談者自身が吟味する必要がありますし、そもそも顧客本位なFPを選びたいものです。
カスタマーリンクス
カスタマーリンクスは生損保だけでなく、住宅ローンの取扱い(ソニー銀行の代理業)や株式・証券の取り扱い(楽天証券の代理業)もあるのが特徴のファイナンシャルアドバイザー会社です。全国に法人保険代理店が約3万社ある中、銀行・証券の扱いもあるのは10社程度で、その中の1社がカスタマーリンクスです。

保険チャンネル、マネードクターのFPの資料や提案内容を踏まえ、改めて4年前の担当FPにLINEで連絡し、相談することにしました。

4年ぶりの連絡ですが、覚えていていただき、非常に丁寧に対応いただけました!
カスタマーリンクスの担当FPは、資産運用も実際の保有銘柄をベースにした利率で計算、退職後の企業年金も相談者の制度にあわせて計算という前提条件の正確さに加えて、使用しているソニー生命のソフトの精緻な資料が私たちの好みにあっていました(ちなみに、同じカスタマーリンクスでもFPによって使うソフトや計算方法は異なるとのことです)。


私達の担当FPの場合、初回面談の前に年収や家計などのヒアリングシートを返信し、それをもとに初回の打ち合わせを行います。
私たちの場合は、あわせて源泉徴収票や確定申告書類、企業年金の制度と試算表の資料を事前にお送りしました。先方もライフプランを作成しやすいので、準備しておくのがオススメ。
資料で分かることはあらかじめ伝わっているため、初回打ち合わせでは、不明点や詳細の確認などに時間をかけることができ、細かいオーダーなど他のFPよりも濃密な打ち合わせが行えました。

今回はマネードクターと同じく第3子を想定し、①第3子が生まれて今の家にそのまま住み続けるパターン、②第3子が生まれて2年後により広い家に住み替えるパターン、③第3子が生まれてもそのまま住み続け、定年後に住み替えるパターン、そしてそれぞれの途中で死んだパータンと計6パターンを依頼しました。
キャッシュフロー表
プランにあわせて①~③がありますが、項目などは同じなので②のパターンを掲載しておきます。

①~③それぞれに万が一時のキャッシュフロー表が用意されています。

年度別収支グラフ
カスターリンクスの資料で分かりやすいのが、年度別収支グラフです。項目ごとに細かく分かれており、さらに色分けされているので、支出の中で項目ごとに占める割合を確認しやすいのが特徴。
こちらは②の第3子誕生後に住み替えるパターン。

③定年後に住み替えるパターン。

定年後に住み替える場合は、住宅ローンが組みにくくなるために現金一括の想定、かつ毎年の物価上昇率を2.5%で置いているために、62歳時点の建築費で支出が突出するようなグラフになります。

これは果たして払えるのか…?というのを見るのが資産残高です。
資産残高グラフ
まずは②の第3子誕生後に住み替えるパターン。
全く問題ありません。第3子+住み替えでも100歳時の資産は8億近くになります。

③定年後に住み替えるパターン。

62歳で住宅費用を現金で支払うために資産残高は一気に減少しますが、100歳まで問題なくプラスです。
なお、①のパターンは載せていませんが、住み替えのない①は当然全く問題ないプランでした。

むしろ大規模な相続対策がいるレベル…。
万一時必要保障グラフ
カスタマーリンクスの場合は、万一時のキャッシュフロー表のほか必要保障グラフが付属します。
こちらは②の第3子誕生後に住み替えるパターンの必要保障額。

例えば、40歳で死亡した場合は1億9,000万円の保障が必要、70歳であれば8,000万円の保障が必要ということです(8,000万というとかなり大きな金額に思われますが、毎年2.5%ずつ物価上昇を加味した数値です)。
ここから、金融資産を差し引いた金額が正味の不足額(保険等で準備が必要な金額)ということになります。
ライフプランの課題と提案内容
ライフプラン診断の結果は、①〜③いずれの場合も問題なしということでした。
万一時保障額は②のパターンで40歳時で1億8,000万円と大きいものの、金融資産が企業年金・死亡時退職金等含めるとほぼ同等の金額になることから、保険はなくても何とかなるということでした。
ただし、上記の金額に住宅ローンは含まれていません。わが家はペアローンのため、死亡した側の住宅ローンは団信で免除になりますが、相手方のローンは残ります。自分のローンは自分の収入で問題なく払える金額ですが、それはあくまで夫婦健在のフルタイム勤務時の話です。片親になった場合は子供が小学校を卒業するまでは、時短などでどうしても収入ダウンになる確率は高い。
そのため、どちらかが死亡した際に、相手方のローン残高に相当する保険に夫婦それぞれ加入することにしました。
加入したのは、FWD生命の収入保障保険。必要保障額が子供の成長にあわせて減ることにあわせて、受け取る保険金も減る仕組みになっている合理的な保険です(そのため保険料も通常の生命保険と比較して割安なため、非常に人気の保険です)。

月々数千円で相手のローン残債を帳消しにできるなら安心料としてはアリかなと判断しました。
保険金を決める際は、加入時の物価で考えがちですが、名目物価が上昇すれば実質的な保険金額は目減りしています。例えば、国立大学の学費(約53万円/年)の値上げが検討されていますが、これが報道のように150万円/年に上がっても、加入していた保険金の支払額が上がるわけではありません。
物価上昇のリスクも踏まえて、保険金額を考えることが大切です。
3社のFPを比較したまとめ
3社のFPに相談した結果、分かったことです。
- 作成するライフプランの質や提案内容はFPに依存する
- 資料の内容は各FPが使用するソフトで異なり、相談者によって好き嫌いが分かれる
本来、前提となる収入や資産、ライフイベントが同じであれば、計算の結果であるキャッシュフローは同じになるはずです。しかし、実際には物価上昇や資産運用利回りを加味するか、加入している保険や年金を加味するかなどで結果は異なってきます。
ライフプランは将来の必要額を把握し、そこから住宅予算を決定したり、リスクに備えるためのものですから、可能な限り精緻なものが望ましいと言えます。
これはソフトの違いもありますが、それ以上にFPがどれだけ相談者に寄り添って丁寧にライフプランを作成しているかによるところが大きいです。
提案内容も然りで、提案者に寄り添った提案をしてくれるかどうかはFP次第と言えます。カスタマーリンクスのFPは、保険の商品そのものはもちろん、必要な理由や金額なども合理的で納得いくものでした。
複数のFPに相談する価値はある?
個人的には、複数のFPへの相談はあまり意味がないと感じます。
基本的にはヒアリングと前提条件であれば、出てくるキャッシュフローや資産残高は同じ内容になります。

ライフプランの作成は計算なので、恣意的な要素があまり入り込まないのです。
ということは、「精緻にライフプランを計算してくれるFPに相談すれば事足りる」というのが私たちの考えです。
逆に、今回当たった保険チャンネルの担当のようなFPに複数人相談したところで時間の無駄だと考えます。

初回面談でヒアリングされる内容はどのFPでもほぼ同じだしね…。
家族構成、月々の収入、支出、資産、保険の加入状況、ライフイベント…。
もちろん、セカンドオピニオン的に聞いてみたいということであれば、無料ですし複数のFP相談を利用するのはアリだと思います。
まとめとFP選びのポイント
私たちはカスタマーリンクスの担当FPの資料が一番あっていました。
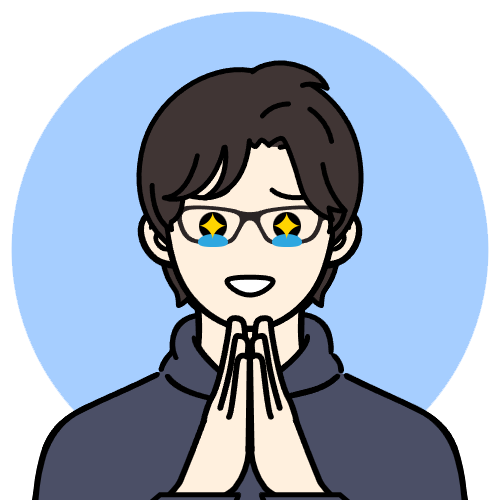
住み替え有無や時期の違いでライフプランを作り分けてもらえたし、何といっても前提条件の置き方が実際の資産内容を反映しており、シミュレーション結果も精緻!
また、提案内容も納得いくものだったことも大きいです。
今回複数のFP面談を経験して、良いFPを選ぶためには以下の基準を考慮すると良いのではないかと思います。
- 知識: FPが持っている専門知識の多さ・深さ。
- 提案資料の質: 提案資料が分かりやすく、具体的であるか。
- 提案の寄り添い度: 課題解決の提案が相談者のニーズに寄り添ったものであるか。
- 継続的な相談: 今後も継続して相談できる関係性が築けるか。
提案資料の質は特に重要な要素です。本記事で繰り返し述べたように、ほとんどのFPは自分のアウトプットがどのようなものか公開しておらず、相談希望者はFPを選ぶ基準がないような状態です。
だからこそ、本記事では各FPのライフプランと提案の違いを比較できるように公開しました。
課題解決の提案が、本当に相談者の課題に寄り添ったものなのか、というのもポイント。一番の懸念点は、相談者に不要な保険や証券を、販売手数料が高いからとFPの都合で提案されるないかといことです。実際、報道されているようなFPパートナー社と生保各社の関係からは、相談者を軽視した保険の勧奨が疑われます。
相談者の側も、保険そのものの必要性はもちろん、提案された保険商品と同種の保険商品を比較して、保険料が安いか、支払条件はどうなっているのかなど細かくチェックすることが必要です。
また、継続的な相談が可能かどうかも重要な要素です。ライフプランの作成は一度きりのものではなく、ライフステージの変化(出産や受験・進学、両親の介護や死亡など)にあわせて見直していくべきものです。
本記事で紹介したように、各FPが作るライフプランは大きく異なっており、ライフプランを見直したくなったときに違うFPに相談すると、前提などプランの連続性がなくなってしまいます。
繰り返し何度も継続的に相談できるFPが理想と言えます。
私たちのFP担当をご紹介できます
本記事で紹介したように、私たちには4年前にもお世話になったカスタマーリンクスの担当が一番合っていました。
本記事を見て、カスタマーリンクスの担当にFP相談をしてみたいという方には、同じ担当FPをご紹介させていただきます。
ご紹介することは担当FPからも快諾いただいています。簡単にプロフィールも乗せておきます。
- 1962年12月生まれ(61歳)
- 資格:2級FP技能士、AFO、住宅ローンアドバイザー、銀行代理業取扱資格者、公的保険アドバイザー、損害保険取扱資格、証券外務員二種
- 半導体メーカーのロームに10年間勤務後、ソニー生命に転職してライフプランナーを開始。
独立や生命保険会社勤務、メガバンク出向などを経てカスタマーリンクス所属。 - 得意なこと:ライフプラン分析に基づくファイナンシャルプランニング、ライフプラン分析に基づく住宅ローンアドバイス、相続対策、資産運用、生命保険アドバイス
本記事で紹介したように、ライフプラン分析が非常に精緻で信頼できるFPです。30年以上のFPとしての経歴があるため信頼感も抜群で、相談しやすい方です。
もちろん、相談料は無料です(相談回数にかかわらず何回でも無料)。ライフプラン分析を通じて、課題がある場合は、課題解決の提案はされると思いますが、相談者に寄り添ったご提案をしていただけますし、最終的にどうするかは相談者次第なのは、通常のFPと同じです。
担当FPの推しポイントをまとめておきます。

当ブログでは、私たち自身がオススメできると思ったことや有益情報は可能な限りシェアするのがポリシーです。
- 生前贈与あり、住み替えなどの複雑なライフプラン設計にも対応
- ヒアリングの丁寧さ、ライフプラン設計の精緻さはピカイチ
- 押し売りなどではなく相談者に寄り添った提案の実施
- カスタマーリンクスは、保険に加えて証券、銀行代理業も取得しており提案の幅が広い(保険、資産運用の提案以外に住宅ローン借換などの提案も可能)
- ライフステージの変化にあわせて、継続した相談やプランの見直しが可能。
打ち合わせはZOOM面談、資料のやり取りはメールで行いますので、全国対応可能とのことです。
住友林業とは関係のないFPですので、住友林業検討者はもちろん、他のハウスメーカー/工務店検討者や、既に引き渡しを受けて住んでいる方からの相談も歓迎とのことでした。
FP相談に関する質問
X(旧Twitter)などでいただいた質問をまとめておきます。
- Q相談は何回でも無料ですか?
- A
無料です。
- Q相談の流れを教えてください。
- A
基本的に本記事で紹介した通り、1回目:ヒアリング、2回目:ライフプラン分析提示、3回目:課題解決提案の3回の打ち合わせです。
- Q保険などに加入する予定はないのですが、相談しても大丈夫でしょうか。
- A
大丈夫です。ライフプラン分析・診断を行い、課題があればご提案させていただくとのことですが、話を聞いた上でそれを受け入れるかどうかは相談者の自由です。
- Qライフプランの資料はもらえますか?
- A
EメールでPDFデータを送付いただけます。
FP担当の紹介依頼方法
ご相談希望者は、下記のフォームに入力・送信をお願いします。
私たちが適当な形で紹介して、担当FPにご迷惑をおかけする形にはしたくないため、お名前(姓だけで結構です)とEメールアドレスの2点だけ最低限の情報として、ご入力をお願いします。
もちろん頂いた情報は、本紹介以外の目的以外には利用せず、担当FPに連絡後は即時削除いたします。
- フォームへの入力
本記事の紹介依頼フォームに必要事項を記入・送信してください。
- kikorist夫婦からのメール連絡
フォーム送信後24時間以内に、kikorist夫婦から担当FPの連絡先をお伝えします。
原則相談者には担当FPからご連絡しますが、万が一連絡がない場合は、kikorist夫婦のメールに返信いただく形でご連絡いただくか、お伝えするFPの連絡先に依頼者から直接ご連絡ください。
- カスタマーリンクスの担当FPからご連絡
カスタマーリンクスの担当FPからEメールでご連絡させていただきます。以降は担当FPと相談依頼者で打ち合わせ日程を決めて打ち合わせをお願いします。以後kikorist夫婦への連絡や報告などは不要です。
FP紹介依頼フォーム

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。



























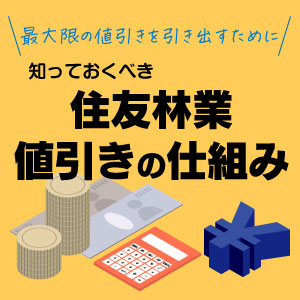







コメント