当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
住友林業で建築中のkikorist新邸での「ホームシアター導入記」シリーズ。本シリーズではkikorist新邸という実例を通してホームシアターの導入過程を丁寧に紹介していきます。

本記事では3階のセカンドリビングへのホームシアターの導入の前提となるプロジェクターの選び方について解説します。
プロジェクターはテレビと比べて敷居が高いと思っている方が多いのではないでしょうか。
下で詳しく解説しますが、プロジェクターはテレビとは映像を表示する仕組みが全く違うので、製品選びが難しい面があります。
この記事では、プロジェクターの知識が0の超初心者でも、ホームシアターに最適なプロジェクターが選べるようにプロジェクター選びの知識について解説します。
プロジェクターとテレビの違い
映像表示の方法、投影サイズ
テレビは画面に映像を表示された映像を直接見る機器
(直視型と言います)に対して、プロジェクターは映像をレンズを通してスクリーン(や壁)に投影し、その投影されたスクリーンを見る機器(投射型と言います)です。

テレビとプロジェクターの違い
テレビは画面のサイズ=映像のサイズになるのに対して、プロジェクターの場合は映像のサイズはレンズのスペックや投射距離によって変わります。

プロジェクターの画面サイズはレンズと投射距離で決まる
テレビは物理的な画面の大きさに制約されますが、スクリーンに映すプロジェクターには画面の大きさの再現がありません(一応最大サイズはありますが400インチとか…)。
テレビでは100インチのモデルが200万円近くもしますが、プロジェクターであれば10万円以下のモデルでも100インチの投影が可能です。機器の大きさや重さも段違いです。
ただし、どれくらいの画面サイズで投影できるかどうかは、プロジェクターのスペックや設置に左右されます。プロジェクターが取っつきにくい点が、実際にどのくらいの大きさで写せるのかが、テレビと違って分かりにくいところです。

テレビは画面のサイズ=映像のサイズなので製品選びが簡単だけど、プロジェクターはどれくらいのサイズの映像が写せるか、レンズのスペックと設置する位置で計算してみないと分からないので、製品選びが難しいのです。

プロジェクター=テレビを超える大画面、と認識しがちですが、設置スペース次第ではテレビよりも小さな画面になってしまう…ということも十分ありえます。
スペックと設置環境が揃ってこその大画面なのです。
テレビで画面サイズが重要なのと同様、プロジェクターでも投影できる映像サイズは重要です(当然ですが…)。プロジェクターの画面サイズや設置環境の検討が、プロジェクター選びのポイントかつ初心者が躓きがちなところなので、記事後半で詳しく解説します。
明るさ
テレビは画面もしく画面の直下に光源があり、それを直接見る直視型ですので、とても映像が明るいです。

テレビとプロジェクターの違い

と、言っても普段テレビだけ見てると当たり前で分かりにくいと思うけど…
それに対して、プロジェクターは光源を直接見るのではなく、スクリーンに投影された映像を見る投射型の機器です。明るさに力を入れている機器であれば、昼間のリビングでもある程度見えるプロジェクターもありますが、一般に同じ環境であれば、プロジェクターはテレビより確実に見にくくなります(画面が白っぽくなる)。

明るいところで見にくいのがプロジェクターの欠点。

プロジェクターは明るい環境が苦手
特に、スクリーンの正面に窓があるような環境はプロジェクターにとっては最悪と言えます。

プロジェクターは(モデルにもよりますが)、暗くして見るもの、と考えていただいたほうがいいと思います。
テレビチューナー/スピーカーを内蔵しない
テレビは(当然ながら)テレビ放送のチューナーやスピーカーを内蔵していますが、プロジェクターはチューナーを内蔵していません(PC用のモニターと同じと考えると分かりやすい)。カジュアルモデルでは簡易的なスピーカーを内蔵するモデルが増えてきましたが、ハイエンドモデルのプロジェクターにはスピーカーは搭載されていません。
プロジェクターでテレビを見るためには、別途BDレコーダーなどが必要で、プロジェクターとBDレコーダーをHDMIケーブルで繋ぐ必要があります。
最近はAndroid OSを搭載したプロジェクターもあるので、単体でも動画配信サービスであれば利用可能なモデルもありますが、リアルタイムでテレビ放送を見るとなると、別途BDレコーダーが必要です。
起動に時間がかかる
プロジェクターは起動させてから画面が一定の明るさになるまで時間がかかります
。最低30秒~1分程度はかかるので、朝のちょっとした時間にニュースを見る、といった使い方には全く向きません(加えて、チューナーの起動が必要だったり、明るい環境では見にくいという問題も…)。
それでもプロジェクターには大画面というメリットがある
これまで挙げたような様々な欠点がある一方で、それでもなぜプロジェクターを導入するかと言えば、やはりテレビでは実現できない大画面の魅力があるからです。
現状のテレビは最大でも100インチ、価格は200万円です。それに対して、プロジェクターはFHDモデルで10万円程度、4Kモデルでも20万円以内で120インチの大画面での表示が可能です。

テレビでは価格的にも物理的にも絶対に越えられない壁…!
「プロジェクターは腰を落ち着けてじっくり見るもの」と考えればこれ以上の映像体験はない
と思います。
プロジェクターの仕組み
プロジェクターには必ずランプやLEDといった光源があり、それを映像デバイスに当てて(もしくはデバイスを透過させる)赤・青・緑の光の三原色を作り出し、それをプリズムやミラーなどの光をコントロールする素材を使って集めてレンズからスクリーンに向かって投射する仕組みになっています。

プロジェクターの仕組み
ここでは、プロジェクター選びで重要な、光源、映像デバイス、レンズについて解説します。
光源
プロジェクターの光源には高原には、主に水銀ランプ、LED、レーザーの3種類があります。
それぞれの違いは下記の通り。
| 光源の種類 | 特徴 |
| 水銀ランプ |
|
| LED |
|
| レーザー |
|
映像デバイス
映像デバイスは、液晶方式(3LCD方式)、DLP方式、LCOS方式(反射型液晶方式)の3種類があります。それぞれの違いは下記の通り。
| 方式 | 特徴 |
| 透過型液晶方式 (3LCD方式) |
映像を作り出すデバイスに透過型液晶パネルを使用する。 映像を映し出す原理は、光源のランプを一旦、光の三原色である赤色、緑色、青色に分解。 透過型液晶パネルで各色の映像を作った後、プロジェクター内で合成して、1組のレンズから投写する。
|
| DLP方式 | 半導体の開発と生産で世界的大手のテキサス・インスツルメンツ(TI)社が生み出した、DMD(Digital Micromirror Device)を核とする方式。 DMDとは、半導体の上に画素数分の小さなミラーを形成したデジタルデバイス。光原からやって来た光に対し、ミラーの方向を変えることで光のオンとオフをコントロールして映像を作り出す。 家庭用はDMDを1枚使用する単板式が主流で、RGBはカラーホイールと呼ばれるミラーを高速回転することで作りだしている(RGBを高速で切り替えて、時分割している)。
|
| LCOS方式 (反射型液晶方式) |
映像を作り出すデバイスとして反射型液晶パネルを使用する。 映像を映し出す原理は透過型液晶と似ていて、光源のランプを一旦光の三原色である赤色、緑色、青色に分解。 反射型液晶パネルで各色の映像を作った後、プロジェクター内で合成して、1組のレンズから投写する。 透過型液晶と異なるのは、各画素を駆動するための配線が、画素の裏面に位置するため、画素間の隙間を狭くすることができ、画素の格子が目立たず滑らかな映像が得られる。
|
レンズ
レンズのスペックによって、そのプロジェクターが投影できる画面の大きさが決まります
。
一般的なモデルは、100インチの大きさを投影するためには約3mの投射距離が必要ですが、これはレンズの性能によります。

100インチで写すために、プロジェクターAは最低3m必要で、プロジェクターBは最低2.8mでいい場合もあるってことね。
設置する必要にあったスペックのレンズを選ぶことが重要です。
プロジェクターのスペックの見方
プロジェクターのスペック表で特に重要なのは、映像の解像度、明るさ、投射距離です。
上記を踏まえた上で映像デバイス(方式)や光源を選ぶのが良いと思います。
ここではkikorist夫婦オススメのEPSON 4K対応液晶プロジェクター EH-TW7000を例に紹介したいと思います。
以下はEPSONウェブサイトにあるEH-TW7100の仕様表の一部を抜粋したものです。
| 方式 | 3LCD方式 |
| スクリーン解像度 | 4K(注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 |
| 入力対応解像度(最大) | 4K |
| 有効光束(白の明るさ) | 3,000lm(最大) |
| カラー光束(カラーの明るさ) | 3,000lm(最大) |
| コントラスト比 | 100,000:1 (注1) |
| 投写レンズ | 1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm |
| スクリーンサイズ | 40型~500型 |
| 光源 | ランプ |
スクリーン解像度
現在のホームシアター向けのプロジェクターの解像度には、フルHD(FHD)、疑似4K、リアル4Kの3種類があります。
フルHDは1080ドット×1920ドットで、Blu-rayディスクや、Nintendo Switchの解像度です。
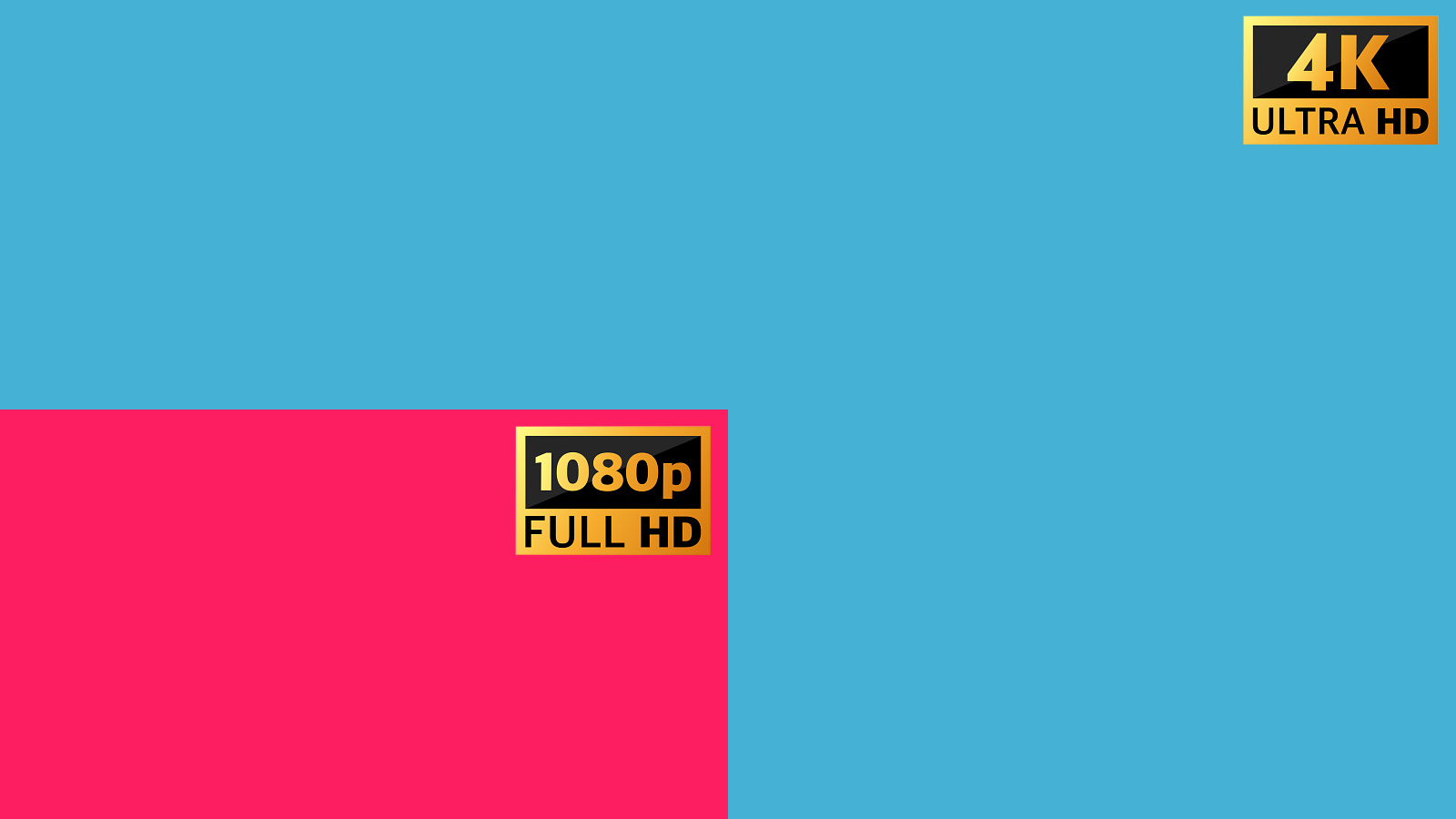
解像度の比較
4KはフルHDの縦横それぞれ2倍の2060ドット×3960ドット、面積では4倍の解像度となります。Ultra HD Blu-rayやPlayStaton5などの最新のゲーム機の解像度となり、今後のスタンダードとなる解像度です。
4K解像度には実は2種類あり、フルHDの映像デバイスを超高速で左右上下に動かす(ずらす)ことにより、疑似的に4K相当の表示を実現した疑似4Kと、映像デバイス自体が4Kのリアル4Kがあります。

Kエンハンスメントテクノロジー(出典:EPSON)
EH-TW7100は液晶パネルは1920×1080で、それをR(赤)G(緑)B(青)の3枚使っており、パネル自体はフルHDですが、それを画素ずらしにより疑似的に4Kで表示しているため、「4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します」と記載されているわけです。
疑似4Kも人間の目では認識できない速さで映像を表示しているのですが、その原理上4倍ではなく、0.5画素ずらしでは液晶パネルの√2倍の解像感しか増えないために、映像の精細さではやはりリアル4Kモデルには劣ります。
※EPSONのハイエンドモデルは2716×1528の液晶パネルを使っており、これの√2倍で4Kの再現が可能です。
解像度では抜群のリアル4Kですが、コストが高い、ドットを細かくするために映像が暗くなる(ドットの格子が多くなる分開口率(=光が通る部分の面積比率)が下がる=暗くなる)、それを補うために強力な光源を使う→ファンの騒音が大きくなるというデメリットもあります。
疑似4Kの最大のメリットは価格です。フルHDの少し上の価格でそれより高い解像度が得られるのがメリットです。
個人的には、最高の映像体験にこだわるのであればリアル4Kモデル、コストパフォーマンスを重視するなら疑似4Kモデルだと考えます。
明るさ
リビングで明るい環境での視聴も重視するなら、出来るだけ明るいプロジェクターを選びたいところです。明るさの単位はlm(ルーメン)で表され、2800lm以上であればかなり明るいモデルと言えると思います。
暗くして見るのであれば明るいプロジェクターはいらないかというとそういうわけではなく、明るいプロジェクターであれば、鮮烈な発光などが表現でき高いコントラストで表示できるので、暗い環境でもやはり明るいプロジェクターのほうが豊かな映像表現が可能です。
EH-TW7100は3000lmと一般向けのホームシアタープロジェクターとしては最高クラスに明るいモデルなので、完全な暗室環境にしにくいリビングシアターでもオススメできますし、映像が明るいので昼間であってもある程度映像が見れます。
投射距離
投射距離は画面の大きさを決める重要な要素
です。これはレンズのスペックによって決まります。
一般的なプロジェクターの場合は、100インチの投影に最短3m程度必要で、ズーム機能を搭載しています。ズーム機能を使えば、投射距離が同じでも多少は画面の大きさが変えられるようになります。また、同じ大きさの画面サイズであっても、投射距離を調整することも可能です。
EH-TW7100の場合、スクリーンサイズは「40型~500型」とありますが、これは投射距離によります。500インチで写すためには10m以上離れる必要があるので、一般家庭では難しいと思います。
レンズのスペックは 「1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm」とありますが、ズームが付いていると分かれば、数字の意味が分からなくても問題ありません。
プロジェクターの場合、スクリーンサイズと投射距離の一覧がスペック表として必ず付属しています。
EH-TW7100の場合は下記の通り。
| スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
|---|---|---|---|---|
| 最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
| 60型 | 133×75 | 175 | 285 | 7 |
| 80型 | 177×100 | 235 | 381 | 10 |
| 100型 | 221×125 | 295 | 477 | 12 |
| 120型 | 266×149 | 354 | 574 | 15 |
| 150型 | 332×187 | 444 | 718 | 19 |
| 200型 | 443×249 | 593 | 958 | 25 |
| 300型 | 664×374 | 891 | 1439 | 37 |
見方としては、100インチの画面(画面サイズ221×125cm)を表示するためには、最短の投射距離として295cmが必要と書いてあります。さらに、ズーム機能を使えば、投射距離が295~477cmの間であれば、100インチで写せるということが分かります。

表にはズームの両端の値しか書いてありませんが、端から端の間は無段階で調整が可能です。
あるいは、スクリーンまでの投射距離として、4mが確保できるのであれば、およそ90インチ(最長の場合)~140インチ程度(最短の場合)のサイズで写すことが可能、ということが分かります。
この表の見方が分かれば、表示させたいサイズから必要な投射距離を計算することも可能ですし、逆に確保できる投射距離から表示ができる画面サイズを計算することも可能です。
なお、投射距離はレンズの表面からスクリーンまでの距離で、プロジェクターの奥行きやケーブルの奥行き(コネクターが背面にある場合)は考慮していませんので注意が必要です。

100インチで295cmでも、実際には+プロジェクターの奥行き31cmやケーブルの接続スペースが必要になるということね。
プロジェクター設置場所の決め方
プロジェクターの設置位置の決め方は2通り。
画面サイズから必要な投射距離を求める方法
と
プロジェクターの設置位置から画面サイズを決める方法
の2種類です。
画面サイズから必要な投射距離を求める方法
プロジェクターを導入するにあたって、どれくらいの画面サイズで見たいか、もしくはどれくらいのサイズのスクリーンが設置できるか、から投射距離を決める方法です。
例えば、「せっかくプロジェクターを入れるなら120インチのスクリーンで入れたい!」と考えているとします。
その場合は、EH-TW7100の場合、投射距離がは354~574cmの間になっていればいいことが分かります。
| スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
|---|---|---|---|---|
| 最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
| 60型 | 133×75 | 175 | 285 | 7 |
| 80型 | 177×100 | 235 | 381 | 10 |
| 100型 | 221×125 | 295 | 477 | 12 |
| 120型 | 266×149 | 354 | 574 | 15 |
| 150型 | 332×187 | 444 | 718 | 19 |
| 200型 | 443×249 | 593 | 958 | 25 |
| 300型 | 664×374 | 891 | 1439 | 37 |

354~574cmが確保できれば、プロジェクターの位置は問わないので、間取りと相談しながら邪魔にならない位置にプロジェクターを設置すればOK。
ただ、その際、120インチのスクリーンが設置できるスペースがあるかは重要です。120インチの画面サイズは266×149cmですが、スクリーンの余白が必要なため、実際に設置に必要な横幅は少し長くなります。
例えば、私も導入予定のシアターハウスの120インチスクリーンであれば、横幅センチ270.7cmが必要です(天井はケース部含めて278.8cmが必要)。

投射距離が確保できても、スクリーンの設置スペースが確保できなければ意味がないので注意しましょう。
プロジェクターの設置位置から画面サイズを決める方法
続いて、プロジェクターの設置位置が、間取りの関係で決まっている場合です。
例えば、設置位置からスクリーンまでの距離が3.5mと決まっているとします。
| スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
|---|---|---|---|---|
| 最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
| 60型 | 133×75 | 175 | 285 | 7 |
| 80型 | 177×100 | 235 | 381 | 10 |
| 100型 | 221×125 | 295 | 477 | 12 |
| 120型 | 266×149 | 354 | 574 | 15 |
| 150型 | 332×187 | 444 | 718 | 19 |
| 200型 | 443×249 | 593 | 958 | 25 |
| 300型 | 664×374 | 891 | 1439 | 37 |
EH-TW7100の場合、3.5mの距離からズームで調整できる画面サイズは、80インチ弱(70インチくらい?)~120インチ弱(120インチに4cm不足)ということが分かります。
スクリーンサイズとしては、80、90、100、110インチから選ぶことになります。

見たいサイズやスクリーンの設置スペースと相談しながら決めます。

120インチのスクリーンを選んで、ズームのワイド端いっぱいいっぱいの118インチくらいで映すというのもあり。
スペック表の見方が分かればプロジェクターは難しくない
これまで見てきたように、各プロジェクターでの投射サイズと画面サイズは必ずメーカーのウェブサイトなどに掲載されているので、見方さえ分かっていれば、設置位置やスクリーンサイズの大きさを決めることはそれほど難しくはありません。
必要な投射距離が十分確保できない場合は?
EH-TW7100のレンズの最短投射距離のスペックは標準的ですが、ズームの調整範囲は1.6倍と広めで、設置の自由度が比較的高いので、万人にオススメできるモデルです。

とはいえ、EH-TW7100の場合、100インチで写すためには約3mが必要なのよね。
投射距離が3m未満しか確保できないけれども、100インチ越えの画面サイズが欲しい場合は、「超短焦点レンズ」を搭載しているプロジェクターがオススメです。

超短焦点レンズとは、短い投射距離でも大きな画像が表示できるワイドなレンズという意味。
超短焦点レンズ搭載モデルは、スクリーン(壁)の少し手前に設置するタイプが多いです。
の設置イメージはこんな感じ。

EH-LS500B
ほかには4Kに対応したSONYのVPL-VZ1000など。
SONY ホーム用超短焦点プロジェクター VPL-VZ1000
超短焦点タイプはスクリーンまでの距離は少なくて済みますが、スクリーン(壁)から少し離した位置に設置する必要があるので、邪魔になったりしやすいのがデメリット。

スクリーン(壁)から少し離す必要あり

超短焦点とはいえ、さすがにスクリーン(壁)ぴったりにくっつける、というわけにはいきません。
また、超短焦点という特殊なレンズを搭載している関係で、ズームができないモデルがほとんどです。ズームができないということは、設置位置=投射距離で、投影サイズが自動的に決まってしまい、サイズの調整ができないということ。

設置位置が決まっていれば、画面サイズは自動的に決まりますし、画面サイズが決まっていれば設置位置も決まってしまいます。
そういう意味では、超短焦点モデルは、設置できる環境を選ぶというか柔軟性がほぼないと言えます。
光学的にはちょっと無理をしている部分なので、同じ価格帯なら通常のプロジェクターと比べて画質が低かったり、同じような画質を求めると高額になったりします。

通常モデルで設置できない場合の最終手段と考えていただければ。
据え置き型で短焦点でオススメというかほぼ唯一の商品がViewSonicのX10-4Kで、kikorist新邸ではこちらを導入します。
約2mで120インチの投影が可能な上に、価格も16万円程度と手頃。
ただ、ズーム機能はやはりありませんので、設置位置やスクリーンサイズは綿密に計算して決める必要があります。

実際の設置位置の検討は次回紹介します。
スクリーンについて
プロジェクター専用スクリーン
スクリーンについては、プロジェクター専用スクリーンが本来は理想です。
プロジェクター用のスクリーンは、プロジェクターの光を綺麗に反射するような表面加工が施されており、やはり画質にこだわって綺麗に見るなら専用品が一番です。
スクリーンには電動昇降式や手動昇降式、壁に固定するタイプなど様々なタイプがありますので、設置する環境や予算にあわせて選択します。
個人的には電動モデルがオススメです。リモコンで電動で昇降できるので楽なのはもちろん、スクリーンの昇降位置のメモリー機能があり、毎回スクリーンの上下位置を調整する必要がないのがメリット。
オススメは楽天でも購入可能なシアターハウスの製品。シアターハウスは福井県の企業で、国産スクリーンで10年保証。サイズが豊富なのはもちろん、電動やチェーン式、ケースの有無など様々な商品をラインナップしています。
ロールスクリーン
窓や仕切り用の汎用のロールスクリーンを使用する方法です。価格が安いことが最大のメリット。映像の綺麗さでは専用品に劣る点、スクリーンサイズの選択肢が少ない点がデメリットです。

純白で透けにくい素材のモデルを選ぶと比較的見やすいです。
オススメは楽天でも購入できるニトリの遮光スクリーン。
W180なら90インチくらいの画面を写すことが出来ます。

雑誌の情報だと、ロールスクリーンの裏側に投影したほうが凹凸が少なくて綺麗な映像が得られるそうです。
白い壁(=壁紙)への投影
スクリーンを使わず、壁への投影も可能です。その際は、壁紙を純白を選ぶこと、凹凸のない平滑な壁紙を選ぶことがポイントです。
色が入っていると、壁紙の色によって映像の色合いがおかしくなります。
また、壁紙に凹凸があると、投影した映像の焦点があわず、クロスの細かな陰影も影響して、映像がぼけてしまいます。サンゲツなどの壁紙メーカーでは、プロジェクター用の壁紙も用意していますので、プロジェクターを使用するのであればプロジェクター用の壁紙を選ぶのも1つの方法です。

スクリーンが不要なのでコストダウン&見た目スッキリ。
また、プロジェクタースクリーンは10インチ刻みでのラインナップですが(特注除く)、壁紙であれば無段階で画面サイズが選べます。
プロジェクター/スクリーン設置にあたっての準備
プロジェクター/スクリーンの設置にあたっては、設計時にいくつか考慮しておきたい点があります。
天井補強
プロジェクターやスクリーンを天井に取り付けるためには天井補強が必要です。

補強無しに取り付けると、天井が破れて落ちてきたり悲惨なことが起きます…
また、場合によってはスクリーンやプロジェクター部分の掘り込みも依頼しておくといいでしょう。

スクリーンの掘り込み

プロジェクターの掘り込み
コンセントの設置
プロジェクターには電源が必要ですので、必ず電源を天井もしくは天井付近の壁に設けるようにします
。

プロジェクター設置位置と重なってしまうと使えないので、設置位置から少し左右にずらした場所にする必要があります。
また、スクリーンを電動にする場合はスクリーン用の電源も必要です。スクリーンは取り付け予定のモデルのどちらに電源部があるのか確認してください。

今後の入れ替え変更などを考えると左右に設置しておくのもありね。
CD管の配置
プロジェクターとAVアンプはHDMIで接続する必要があります。
プロジェクターの設置位置からAVアンプの設置位置までケーブルが通せるようCD管を配管しておけば、ケーブルが壁や天井を這うということを避けられます。

CD管
(番外編)引っ掛けシーリングに取り付けるモデルも
本来照明を取り付ける引っ掛けシーリングに取り付けられるpopIn Aladdinも人気です。
popIn Aladdinは照明にプロジェクターを内蔵、Bluetoothやスピーカーも内蔵したオールインワンモデルです
。

popIn Aladdin
2世代目のpopIn Aladdin2になって解像度もフルHDとなり、ますます魅力的なモデルになりました。動画配信アプリも入っているので、Amazon Prime Videoなどそのままで動画配信サーズの視聴が可能です。

動画配信サービスに対応
レンズも短焦点タイプなので、2mあれば120インチの画面サイズでの投影が可能です。ただしズームはやはりありません。

popIn Aladdinの投射距離と画面サイズ
本記事のまとめ
本記事ではプロジェクター選び、設置に必要な前提知識を解説しました。
- プロジェクターの魅力は大画面
- プロジェクター選びのポイントは、解像度・明るさ・投射距離
- プロジェクターのスペック表を見れば、必要投射距離や画面サイズの情報が得られる
- 投射距離が取れない場合は、超短焦点モデルがある
- プロジェクターやスクリーン設置のための天井補強、電源、配管を設計時に考慮
次回は、3階のリビングシアターの環境について紹介します。
参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。



























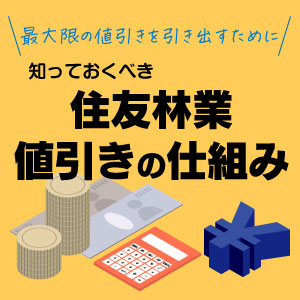

















コメント