当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
に引き続き、ハウスメーカーの選び方、その中でも一番最初に検討すべき工法についてまとめています。
前回は木造と鉄骨造の違いについてまとめていますので、木造と鉄骨造の基本的な長所短所はこちらの記事をご覧ください。
今回は木造と鉄骨造の工法詳細について解説していきます。
ご留意いただきたい事項
以下は私たちがハウスメーカーの選定を進めていくなかで学んだこと、調べたことを中心に記載していますが、あくまで専門知識のないユーザー視点での記載です。
もし誤りがございましたらTwitterやコメントなどでご指摘いただけますと幸いです。
また、個人的な好み・主観が含まれていますので、その点もご承知おきください。
各工法の違いを知るべし
ハウスメーカーの選定に入る前に、今回は注文住宅の工法(=家の作り方)について解説します。
工法から入るのは、どの工法で建てるかを決めることで、自ずとハウスメーカーが決まってくるためです。例えば、住友林業は木造だけ、ヘーベルハウスは鉄骨だけしか取り扱っていません。木造で建てる決めた場合、ヘーベルハウスは選択肢から抜けることになります(逆も然りです)。
※積水ハウス、ダイワハウスなど木造・鉄骨造両方を扱っているハウスメーカーもあります。

ハウスメーカーは大手だけでも沢山あるから、効率よく選定するには工法から入るのが大事。

どのメーカーがどの工法を採用してるかなんて全く知らないで、住宅展示場というハウスメーカーが口を開けて待ってる戦場に突っ込んだ私たちの反省が活かされてるわね。
また、各工法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。各メーカーは当然自社の工法の弱点は把握しており、できるだけ工夫や商品開発でカバーを図っていますが、それでも基本的な工法の特性はどうしても出てしまいます。

例えば、断熱性については明らかに木造>鉄骨です。鉄骨系メーカーも断熱材を増やすなどの工夫はしていますが、木の350倍熱を伝えやすいという鉄という素材の基本的な特性はカバーしきれません。
断熱性を最優先するのであれば、素直に木造を選んだほうが求める性能が高い家になる傾向にあります。
一概にどの工法がベストということはありません
。

全員にとってベストな工法があればどのメーカーもそれを採用するわけで…。
ユーザーが何を重視するかでベストな工法は変わります
。各工法のメリット・デメリットを確認した上で、ユーザーが重視する内容に合った工法を選択することが大事です。

私たちは最終的に木質感やデザイン性などを重視して最終的に住友林業を選んだけど、堅牢性を重視するなら断トツにヘーベルハウスが優れていると思ったわ。
工法を知ることでハウスメーカー選びが楽になる
工法を絞ることによって、たくさんのハウスメーカーが出店している住宅展示場に行く際も、どのハウスメーカーを見るべきなのかが分かり、ハウスメーカー選びが楽になります。

私たちのように車を停めた場所から近くて名前を知ってるハウスメーカーのモデルハウスに順番に入るとか絶対にやめましょう。
入ったら1時間半~2時間は拘束されるので、貴重な時間を無駄にします。

それと、優秀な営業担当についてもらうためには、何も考えずに住宅展示場に行くのはやめましょう。
優秀な営業担当についてもらう方法はこちらの記事にまとめてあります。

住宅展示場は、営業担当が決まった上でのプランの打ち合わせや、展示されている構造モデルを使ったハウスメーカーの特徴説明を受けるためにに利用するのがオススメです。
木造の3種類の工法

主な工法のまとめ
木造には大きく分けて、「軸組工法」、「枠組壁工法」、「次世代工法」の3種類の工法があります。この3種類は同じ木造でも特徴がかなり異なるので注意する必要があります。
軸組工法
「木造軸組工法」は日本古来の工法で、「在来工法」とも言われます。寺社建築に採用されている「伝統工法」を住宅向けにアレンジしたもので、柱を立て、梁を水平に渡し、筋交いという斜めの補強材を使って構造で家を建てます。

出典:SUUMO
軸組工法は主に柱や梁で構造を支えます。この柱や梁の場所はかなり自由が利くので、一般に間取りの自由度が高いと言われています。後々の増築・改築や間取り変更にも対応しやすいのが特徴です。

私たちは最初は「間取りの自由度」っていう言葉の意味がよく理解できませんでした。
ほとんどの方は同じようにイメージが沸かないと思います…。
間取りをゴリゴリいじっている今なら(多少は)理解できるようになったので、別記事で解説したいと思います。
一応本記事の後半でも少しまとめみました。
また、柱・梁の位置がある程度自由に調整できるので、枠組壁工法に比べて、柱と柱の間隔が空いた大空間のある間取りや、大開口の窓を作りやすくなります(枠組壁工法と比較した場合の話で、筋交いが必要である以上、絶対的な部分では鉄骨造には劣ります)。
一方、木造軸組工法は、柱と梁の接合部で切り欠きができ、強度がどうしても低下しますので、耐震性の面では面全体で構造を支える壁工法のほうが有利です。
※軸組工法でも現在では接合部にボルトや金具をある程度使用するようになっており、耐震基準は当然クリアしていますので、相対的な話です。

「仕口」や「継ぎ手」の加工が必要で、構造的に重要な柱や梁を削り取るため、強度を弱めてしまう
枠組壁工法
「枠組壁工法」は角材(2インチ×4インチで作られた木材をツーバイフォーと呼ぶ)と木製パネルで壁や床、天井という面を作り、この面を組み立ててできる6面体の構造をベースに家を建てます。
※より太いツーバイシックス材(2インチ×6インチ)を使い工法もあります。

出典:SUUMO
枠組壁工法の長所短所は軸組工法の逆です。
面で支えるために耐震性には優れますが、その支える面の強度が下がるために大きな窓などを付けることが苦手な傾向にあります。また、構造上外せない壁なども出来てしまうため、軸組工法と比べて間取りの自由度が下がります。

確かに住友不動産の間取りプランは、2×4工法だからか、ほぼ長方形のゾーンだけで構成されてた…。
枠組壁方向の大きなメリットとして、パネルで家を覆うために、高断熱・高気密の住宅にしやすいという点があります。

圧倒的な高断熱・高気密を武器にオーナー急増中の一条工務店は代表的な枠組壁工法のメーカーよ。

高気密の弊害で結露しやすいというデメリットがあるから、一条工務店は換気にも力を入れてる。性能面ではちょっと羨ましい。
次世代工法
ここで紹介する「次世代工法」は、軸組工法の欠点を解消した上位互換の工法として理解しておけばOKです。
住友林業は次世代工法のビッグフレーム構法が主力商品ですが、軸組工法の商品も用意していますので、両方が選べます。

どうでもいいですが、注文住宅で仕様以外は全く異なる家なのに、量産品のように「商品」と表記するのは凄く違和感を感じるのは私だけでしょうか…。
※メーカーがそのように記載しているので公式表記に従いますが…。

「次世代工法」という呼び方も住友林業の呼び方で、何とカテゴライズしたらいいか分からないので便宜上そのまま使っていますが、いい表現があれば教えてください。
私たちは住友林業の施主ですが、別に関係者でも回し者ではないので…。
大きく分けて、住友林業が採用している「ビッグフレーム構法」と、「シャーウッド構法」や「SE構法」などの「金物工法」に分けられます。
ビッグフレーム構法は住友林業だけの構法で、幅560mmのビッグコラム(大断面集成柱)という壁のような柱を使用することで、耐震性を確保しながら、大開口・大空間を実現しています。

ビッグフレーム構法
また、梁や基礎との接合部にはメタルラッチという金物(=金属部品)を利用して強力に接合させています。
もう1つの次世代工法である「金物工法」は、木造軸組構造の接合部に、金属のボルトや専用の受け金具を使うことで、木造軸組み構造の欠点だった接合部の強度を上げ、耐震性を大幅に向上させた工法です。

軸組工法と金物工法の違い
積水ハウスのシャーウッドや、エヌ・シー・エヌが全国の工務店向けに提供しているSE構法が該当します。
ビッグフレーム構法も金物工法も、木造の間取りの自由度や軽さというメリットを活かしつつ、鉄骨なみの強度を実現したのがメリットです。
デメリットとしては、木造の中では建築費が高額になりがちです。ビッグフレーム構法は住友林業のだけの技術ですし、ビッグフレーム構法や金物工法で利用する接合金具を使用するためには、高精度の施工品質が要求されるため、高い技術力が必要だからです。
※金属は木材と違って曲げたり伸縮させたりといったことができないため、組み立て上の誤差が許されない。

結果、費用としては鉄骨造とあまり変わらないか、鉄骨造よりも高くなることもあります。
鉄骨造の3種類の工法
鉄骨造は「軽量鉄骨造」「重量鉄骨造」「コンクリート造」の3種類に分けられます。
鉄骨造に共通する長所短所や木造との比較は前回の記事をご覧ください。
軽量鉄骨造と重量鉄骨造
軽量鉄骨造と重量鉄骨造の違いは、よく使っている鉄骨の厚み(軽量は6mm未満、重量は6mm以上)だと言われますが、それぞれのハウスメーカーで間取りを作ってもらったkikoristとしては、それだけでなく間取りの自由度が大きく違うと感じました。
鉄骨に共通する点として、いずれのメーカーも「型式認定」を取得しているというのがあります。

「型式認定」とは国土交通大臣より指定を受けている認定機関が、建築基準法に基づいた審査を行い、工法が国に認定されているということです。
型式認定を受けているとということは、国から一定のお墨付きを受けている一方で、工法が規格化されており、融通が利きにくいということでもあります。
この融通の利きにくさが、軽量鉄骨と重量鉄骨で間取りの自由度に大きく影響しています。
例えば、重量鉄骨造では非常に太い柱で支えるので、四隅に柱を立てれば、中の壁は1cm単位で自由に設定することができます。
ですが、軽量鉄骨造では重量鉄骨ほど耐荷重がないので、もう少し小さい単位で型式認定を取っており、それによって必要な柱の位置、梁の位置、壁の位置が決まってしまいます。

自由度の違い
結果として、軽量鉄骨造は重量鉄骨造と比較して圧倒的に間取りの自由度が少ないことになります。
注:上記あくまで例ですので、間取りによって必要な柱の数は変わります。重量鉄骨造のほうが軽量鉄骨造より必要柱の数が断然少ないとご理解ください。

間取りを自由にいじりたい私たちにとって、この軽量鉄骨造の型式認定による規格の縛りは非常に厄介なものでした。

リビングの西側をもう1マス増やしたいと思っても、東側部分も増やさないといけないために、東側が別の部屋に干渉したり…。
軽量鉄骨造でも重量鉄骨造でも大開口や大空間は取れますが、この間取りの自由度はかなりの差だと思いました。
費用面では、軽量鉄骨造のダイワハウスよりも、重量鉄骨造のヘーベルハウスのほうが安かったこともあり、ダイワハウスは候補から落としました。

間取りの自由度が低いのに費用が高いっていいとこないじゃん…。
実家がダイワハウスだったから親族割引も適用したのに…。

セラミック外壁とか一応いいところもあったわよ。
コンクリート造

私たちが検討したメーカーにコンクリート造のメーカーがなかったので、まったく研究不足です…。そのため割愛させていただきます汗

大成建設ハウジングや三菱地所ホームが採用しているらしいですが…。
ユニット工法(プレハブ工法)
最後に、主に鉄骨メーカーで採用されている「ユニット工法」についても触れておきます。
ユニット工法は、鉄骨造の一種で、部屋をユニットとして工場で生産し、建築現場では完成しているそのユニットをクレーンで吊るしながら、積み木のように家を建てていく工法です。
工場で建具まで含めて部屋を作り込んでいるので、通常の鉄骨造以上に施工業者(=大工)の技術力に依存する割合が低いことが特徴です。

天然素材を使う木造と比べて、工業製品である鉄骨はただでさえ品質のばらつきが低いのに凄い…。

ただ、工場で生産するため、ユニット=部屋の自由度はかなり低いのがデメリットです。
間取りの自由度よりも品質重視ならユニット工法を採用しているハウスメーカーがオススメです。
ちなみに、ユニット工法のことを「プレハブ工法」と呼ぶこともありますが、これはちょっと紛らわしい言い方です。

プレハブ工法=仮設住宅ではありません。

最初はそう思った。
プレハブというのはPrefabricated(前もって部品などを作る)から由来した言葉で、柱や壁、梁などの部材を工場で生産し、建築現場で組み立てることを指します。現在の大手ハウスメーカーは鉄骨造・木造問わず大なり小なり工場で生産しているため(木造でも柱や梁に使う木材のカットとかは工場で事前に加工しています)、ほとんどのメーカーはプレハブメーカー・プレハブ工法と言えます。
そのプレハブ工法を最も推し進めた工法がユニット工法というわけです。
工法の詳細まとめ
今回は木造・鉄骨造それぞれの工法の詳細をまとめました。
繰り返しになりますが、どの工法がベストかというのは、ユーザーの重視するものが何なのかによって変わります。

堅牢性と間取りの自由度の両立なら重量鉄骨造だし、高断熱・高気密を重視するなら木造枠組壁工法とか。
何を家づくりに求めるか整理ながら検討すると良いです。


決めきれない場合は、私たちのように各工法のメーカーそれぞれにプラン作成・見積を依頼するのもありだと思うわ。

うちは各工法への知識がゼロからスタートしたというのもあります。

正直、実際に打ち合わせてみないと間取りの自由度とか実感できないと思うし。

耐震性は大手メーカーであれば耐震等級3以上は満たしているし、何といっても、優秀な営業担当や設計士であれば、自社の工法の制限も相違工夫とアイディアで予想と期待を超えてくるはずです。
家づくりはどこ(どの工法)で建てるのかも重要ですが、それ以上に誰と建てるかが大事です(詳しくはこちらの記事参照)。

住宅展示場の各メーカーのモデルハウスでは、構造を実際に見れたり、模型などで体験できる仕組みになっているから、興味のある工法のメーカーは訪れてみるといいかも。

オプション盛り盛り、提案仕様どころか完全にメーカー仕様無視のモデルハウスも多いから、広さや内装などは全く参考にならないけどね…。
次回は各ハウスメーカーが実際にどの工法を採用しているのかということと、各メーカーの価格についてまとめていきます。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。



























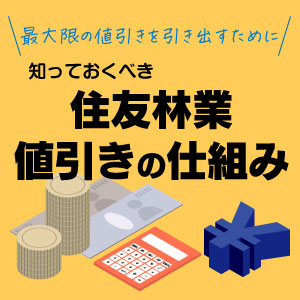










コメント