当ブログ「kikorist日誌」は、kikorist夫婦が住友林業で注文住宅を建てる過程や、家づくりのこだわりポイントを発信・紹介するブログです。
あわせて住友林業の割引が受けられる紹介制度のご案内もしています。
住友林業を検討中の方はもちろん、これから家づくりを始める全ての方に分かりやすく情報を発信しています。
WEBマガジン「イエマガ」でライターとして家づくりの検討過程を月刊連載中。
家づくりに関するリアルタイムの情報、ブログに書ききれない住友林業の小ネタはTwitterで、インテリアなどの写真はInstagramで発信していますので、よろしければフォローお願いします。
【注意事項】当ブログ内の写真、イラスト、文章については、流用・引用を一切認めておりません。
当ブログはアフィリエイト広告/AdSecse広告を利用しています。
住友林業では、以前は施主支給を受け入れていましたが、2024年10月から施主支給が原則不可となりました。

「原則」とあるように、完全な禁止ではなく一部例外があるとのこと。
例外についても本記事で解説します。
本記事では施主支給の概要と、施主支給が原則禁止となった背景について解説します。
施主支給とは
施主支給とは、住宅設備機器や建材などを施主が自分で購入してハウスメーカーに支給することです。
通常、住宅設備機器等はハウスメーカーの納入ルートを通じて、メーカー→ハウスメーカー→現場へと届けられ、費用は取付費なども込みで建築費の一部としてハウスメーカーから施主に請求されます。
この流れに乗らず、施主が品物だけ自分で購入して現場へ届けるのが施主支給です。
施主支給は物品だけ施主が手配して、施工(=取り付け)はハウスメーカーであることが一般的で、これを住友林業では「材のみ」(材料のみという意味)の施主支給と言います。
施工(取付)もハウスメーカーではなく、施主自身もしくは施主が手配した外部業者が行うことを「材工」(材料と施工両方という意味)の施主支給と言います。
ただし、住友林業が許可していない外部業者は建築中の現場に立ち入ることは許されませんから、材工で施主支給する場合はハウスメーカーから施主に家が引き渡されてからの工事となります。外部業者ではなく、施主自身がDIYで施工する場合も責任分担を明確にするために、引き渡し後の取り付けとなります。
施主支給のメリットとデメリット
施主支給のメリット
- 自分好みの商品をハウスメーカーの取り扱いを超えて選べる。
- 同じものであればハウスメーカーで経由するより安い場合が多い。
施主支給に魅力を感じるのは、自由な商品選定と価格です。
ハウスメーカー経由で購入できる商品には限りがあります。一般的な大手建材メーカー(マルホンや大建工業など)の製品なら、個別の特注品として見積を取って採用することもできますが、たとえば楽天のショップが独自に販売しているブラケットライトやタオルハンガーなどは、ハウスメーカーでは取り扱いがありません。こういったハウスメーカーで購入が出来ない商品を使用したい場合、ハウスメーカーの代わりに施主が購入して現場に届ける施主支給で解決できるわけです。
また、同じ商品であれば、ハウスメーカーよりも施主支給のほうが安くなることが多いのもメリットです。商品によりますが、Amazonや楽天の最安値は時には業者の仕入れ価格を割っていることもあるようです

ハウスメーカーの利益が乗っていないから、その分安く入れられます。
施主支給のデメリット
- 傷・不具合が原因のトラブルが発生する可能性がある。
- 仕様や規格、サイズ、必要な取り付け部材を理解して品選びする必要がある。
- 施工会社に施工に関する説明や情報供与をする必要がある。
- ハウスメーカーの保証が受けられない。
- 住宅ローンの対象外。
- 施主が保管・配送する必要がある。
ただ、電気・水道・ガスに関する工事が絡むものに関しては、ハウスメーカーによっては施主支給にかなりナーバスです。

初期不良、水漏れ・ガス漏れなどの際の責任問題があいまいになるためです。
ハウスメーカーが手配した商品ならハウスメーカーの責任で交換ができますが、施主支給の場合は、部品の問題なのか工事の問題なのかの切り分けが必要で、もし部品の問題であれば施主が新しい品物を用意する必要があります。
商品に傷や不具合があったとして、それがメーカーの問題なのか、配送業者の問題なのか、または商品搬入後に発生した問題なのかなどを切り分ける必要があります。たとえ、メーカーや配送業者の問題であっても、交換のために納品に遅れが生じれば現場の作業に大きな迷惑をかけることになります。
また、施主が正しい知識で商品を選択する必要があるのもデメリットと言えます。例えば、LIXILのトイレでは、新設用とリフォーム用、床排水と壁排水、ブースターの有無、寒冷地用と標準地用、ヒーター有無など様々な仕様が存在しており、建てる予定の家にあわせて適切に選ぶ必要がありますが、素人にはなかなか選択が難しい。もし万が一間違って注文してしまったら、返品交換の手間も発生しますし、何より現場に大迷惑をかけてしまいます。ハウスメーカー経由で購入すればこういった余計な心配は不要です。
また、商品によっては、商品以外に取り付け部材(ビスや配管、接手、フィラーなど)を別途用意する必要があったりします。これらも事前に正しく用意ができていないと現場に迷惑をかけてしまいます。施工説明書なども原則施主が用意する必要があります。
また、施主支給された商品が起きたトラブルについては、ハウスメーカーの保証は適用されません。
施主支給は基本的に住宅ローンの対象外となります。例えば、エアコン4台を施主支給するというような場合、その費用は現金支出となるので、手持ちの資金と相談しながら対応する必要があります。
また、原則施主が保管・配送する必要があります。現場に直接配送することはNGで(大工さんなどは受け取りができないため…)、一度施主が受け取って保管し、必要となるタイミングで現場に届ける必要があります。
住友林業で施主支給は2024年10月以降原則不可に
住友林業では以前では施主支給に比較的寛容でした。
2021年に竣工した私たちの場合も、施主支給をそれなりに行っています。
我が家の施主支給の詳細はこちらの記事でまとめています。
ところが、2024年10月以降、住友林業での施主支給は原則禁止のルールとなりました。

もしそれ以降でも「自分は施主支給できた」という場合でも、それは営業担当や生産担当の好意であり、原則禁止がルールとのこと。

あまり大っぴらに言わないほうがいいかもです。
(営業担当や生産担当は公表されたくないはず…)
なぜ住友林業では施主支給ができなくなったのか?
なぜ住友林業では施主支給ができなくなったのか?
これは、前述したデメリットのためだと思われます。
- 傷・不具合が原因のトラブルが発生する可能性がある。
- 仕様や規格、サイズ、必要な取り付け部材を理解して品選びする必要がある。
- 施工会社に施工に関する説明や情報供与をする必要がある。
- ハウスメーカーの保証が受けられない。
- 住宅ローンの対象外。
- 施主が配送・保管する必要がある。
簡単に施主支給と言っても、実は非常に手間がかかっています。
- 商品の受け取り
- 商品の検品
- (不足していた場合)必要な取付部材の購入案内
- 職人への段取り/取付指示
- 職人さんへの施工費用支払い
このように施主支給により現場に負担をかけることが多くなったため、禁止になったとのことです。
住友林業で施主支給できるものは?
住友林業での施主支給は「原則」禁止になりましたが、事情があれば許可されることもあるようです。

例えば、旧家で使用していた思い出の欄間や柱といった、施主様の思い入れがあり、市場で入手ができないものなどが該当します。
逆に言えば、「住友林業で取り扱いがあり、安く導入することだけが目的の施主支給」は認められる可能性がほとんどないと言えるでしょう。

タオルハンガーやトイレットペーパーなどの小物も不可能なのでしょうか?

大手メーカーの商品ではなくて楽天で可愛いものを購入して取り付けたいと思ってたんだけど…。

ルールに照らすと「不可」としか言えませんね…。
ただ、そのくらいであれば営業担当や生産担当が好意で対応していることもあるとかないとか…。
営業担当や現場に迷惑をかけないためにも、あまり無理なお願いをしないようにしたいものです。
本記事のまとめ
本記事では住友林業の施主支給のルールについて解説しました。
もしどうしても施主支給したい商品があった場合、着工合意までに設計担当に施主支給品について説明し、どの場所に取り付けるかといった点も事前に打ち合わせするようにしましょう。
着工後に取り付ける…となった場合、図面上に存在しないために生産担当や建築現場の職人さんに負担をかけてしまうことになります。
可能な限りスムーズに工事が進むよう協力するというのも、施主の1つの仕事と言えます。
参考になれば幸いです。

既に完成してwer内覧会している方のブログは特に参考になるはず。







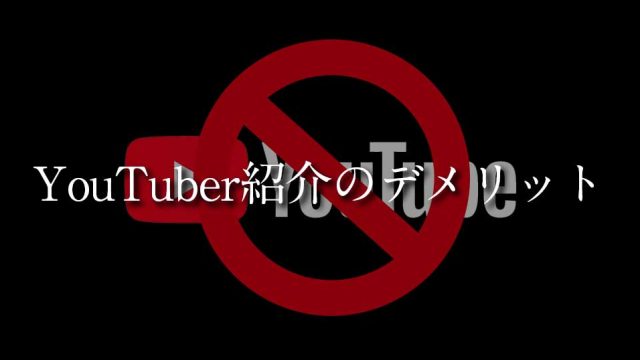



















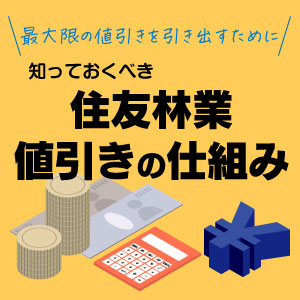









コメント